協調ロボット(協働ロボット)は、人とロボットが安全に共同作業を行う技術として、製造業を中心に急速に普及しています。特に、日本企業のオムロンが、協調ロボットに関する最先端の技術をもつメーカーとして注目されています。
本記事では、オムロンが提唱する協調ロボットのコンセプトを簡単に紹介した後、同社が開発中の最先端の協調ロボットと、その技術を活用した「i-Automation!」のビジネスモデルを解説します。
この記事の内容
.png)
協働ロボットのイメージ(オムロンの特許 JP6866673B2 の図に追記して作成)
「協調ロボット」と「協働ロボット」は似た概念ですが、一般的には「協働ロボット」という言葉がよく使われます。まず、協働ロボットの一般的な定義を説明します。
協働ロボットは上図のようにセンサで作業者の位置を把握し、ロボットの作業域に作業者が近づくと自動的に動作を停止したり、スピードを落とす機能を備えています。この機能をもつことで、従来の産業用ロボットのように「ロボットの作業スペース柵で囲う」といった安全対策が不要になり、人とロボットが空間を隔てずに作業することが可能になります。
協働ロボットの世界市場では、デンマークの「ユニバーサルロボット」がシェアNo.1で、半導体などの工場に加え、医薬品や化粧品などライフサイエンス分野の工場でも利用されています。日本企業でも、ファナックや安川電機、オムロンなどのメーカーが活躍しています。
特にオムロンは、独自の制御技術を生かして協働ロボットを進化させた「協調ロボット」のコンセプトを提唱しています。以下、協調ロボットのコンセプトと具体例を紹介します。
※ユニバーサルロボットの技術戦略については以下の記事で解説しています。
オムロンは同社のHPで、「人と機械の高度協調」という協調ロボットのコンセプトを紹介しています。以下に概要を簡単に整理します。
つまり、オムロンは単に「作業を効率化」するだけでなく、現場で作業する「人」がより良く働くためのロボット開発を目標としているようです。では、具体的にどんな技術を開発しているのか、次項で最新の事例を紹介します。
.png)
作業者の動きを「予測」して動作するロボットのイメージ(オムロンの特許出願 JP2023029629A の図に追記して作成)
オムロンの協調ロボットの技術開発の最新動向を知るため、2023年に出願された JP2023029629A の内容を調査しました。上図のように、作業者の動きをカメラなどのセンサで測定し、学習することで、作業者が次にどう動くかを「予測」するシステムが記載されています。予測した内容に応じて、制御システムがロボットが次に行う作業を指示します。
作業者の状況が工場に設置されたカメラなどを通じてリアルタイムで把握されるので、先述したように「ロボットが状況や作業者の習熟度に応じて作業すること」が可能になります。もはや単なる「ロボット」ではなく、工場全体が「状況に応じてロボットが作業者を支援するシステム」として機能していることがわかります。
このように、工場全体を自動化・スマート化する仕組みは「ファクトリー・オートメーション」や「スマートファクトリー」などと呼ばれます。個人的には言葉だけを聞いても良くわからなかったのですが、具体例を見ることで理解が深まりました。
オムロンは、上記の「工場の自動化」により顧客の課題を解決する独自コンセプト「i-Automation!」を発表しています(2022年1月のリリース参照)。先述の「人と機械の高度協調」もコンセプトに含まれており、関連サービスがすでに4000社近い企業に採用されています。
i-Automation! を導入した企業には、オムロンのロボットとソフトウェアを組み合わせたシステムが提供され、作業の省力化や自動化が進みます。例えばジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社の導入事例では、オムロンの検査装置の導入による品質管理の自動化が進められています。
1つの工程の自動化が進むと、また別の課題が見えてくるので、顧客はその解決のためにオムロンの周辺機器を導入することになります。顧客の課題を解決しながら自社製品を次々に販売する、というのが i-Automation! のビジネスモデルのようです。
キーエンスとオムロンの比較記事で、「制御」がオムロンのコア技術であることを解説しました。 i-Automation! のビジネスモデルは、オムロンのコア技術の価値を最大限に活用する仕組みと言えます。
以上、協調ロボットについて、その一般的な定義やオムロンの独自のコンセプト、最新の特許技術やi-Automation!のビジネスモデルを詳しく紹介しました。すでに単なる「産業用ロボット」のコンセプトを超えて、「工場全体をスマート化するためのロボットシステム」が構築され始めており、製造現場の革新が急速に進んでいます。
今回ご紹介した内容は、弊社の無料メールマガジンで代表の楠浦がお送りした内容の一部を抜粋し、再編集したものです。メルマガではより幅広い情報や、技術的に踏み込んだ内容をご紹介しております。
また、弊社の調査レポート「イノベーション四季報」では、テーマごとのイノベーション情報を総括した資料を提供しています。オムロン以外のメーカーを含メタ協働ロボットの最先端をより詳しくまとめたレポートも、後日リリース予定です。
コラムや調査レポートのリリース情報もメルマガで毎週お伝えしているので、最新情報を入手する無料ツールとして是非ご活用ください。
★本記事と関連した弊社サービス
①無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。半導体関連の技術に関する情報も多数発信しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
②【新規事業・起業・投資の羅針盤 イノベーション四季報™】
イノベーションには「流れ」がありますが、「感覚」では捉えられません。
実際の企業の分析結果を元に「具体的な事例」を読み解いた最新情報を、今後を見通す「羅針盤」として4半期ごとに提供します。創刊号ではGAFAMの分析に正面から取り組みました。巨大企業の戦略を読み解き、その先を攻略したい方はぜひ!
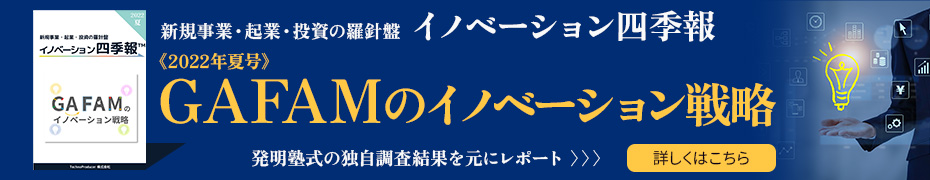
★弊社書籍の紹介
弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
◇本コラムの内容にご興味をお持ちいただけましたら、関連する幅広い情報を盛り込んだ弊社の新刊書籍もぜひチェックしてみてください。本書籍特設サイトはこちら

畑田康司
TechnoProducer株式会社シニアリサーチャー
大阪大学大学院工学研究科 招へい教員
半導体装置の設備エンジニアとして台湾駐在、米国企業との共同開発などを経験した後、スタートアップでの事業開発を経て現職。個人発明家として「未解決の社会課題を解決する発明」を創出し、実用化・事業化する活動にも取り組んでおり、企業のアイデアコンテストでの受賞経験あり。
あらゆる業界の企業や新技術を徹底的に掘り下げたレポートの作成に定評があり、「テーマ別 深掘りコラム」と「イノベーション四季報」の執筆を担当。分野を問わずに使える発明塾の手法を駆使し、一例として以下のテーマで複数のレポートを出している。
IT / 半導体 / 脱炭素 / スマートホーム / メタバース / モビリティ / 医療 / ヘルスケア / フードテック / 航空宇宙 / スマートコンストラクション / 両利きの経営 / 知財戦略 / 知識創造理論 / アライアンス戦略
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略