「発明塾」塾長の楠浦です。
今日も、2025年4月に開講する「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾 公開講座)」に関連する内容を、紹介していきます。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
上記ページから、「詳細資料請求」「説明会動画の視聴」「お申込み」が、それぞれに可能です。
「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾 公開講座)」では、支援者の方に発明塾の手法を学んでいただくだけでなく、「学び方」「指導法」まで学んでいただけたらよいな、と考えております。
お申し込みは受付開始しております。
先着10名様までの募集となりますので、ぜひ参加したい、という方は早めにお申し込みをお願いします。
前回は、「プロ」「仕事のできる人」になるために欠かせない、「暗黙知」のお話をしました。
まとめると、こんな感じですね。
・熟達者と呼ばれる、いわゆる「プロ」「仕事のデキる方」の共通点は、詳細かつ豊富な知識と共に、それらを使いこなす「暗黙知」を持っている
・「暗黙知の身につけ方」は、プロになれるかどうか、あるいは、そこに向けたスキルアップがうまく進むか、の生命線
・「暗黙知」の存在に気付くための第一歩が「省察」(せいさつ)、ただし、「省察」は「反省」とは異なり「自分なりの成功方程式」を見つける手法
今回は、プロになるため、スキルアップするために欠かせない「暗黙知」獲得の方法について、別の観点から、説明します。
学生向け発明塾で教えていた、あるいは、明示的には教えてないけど、必ずそれらにもとづいて運営されていた、というものが、少なくともあと2つあります。
3つもあると、運営するほうも大変なんですよね(笑)。
でも、少なくともこの3つは厳守しないと、短期間で成長はしないんですよね。
教育学の話です。
この記事の内容
残り2つのうちの1つ目は、「認知的徒弟制」という、手法というか仕組み、考え方です。
これは、身体的スキルの習得を目的にした伝統的な徒弟制(伝統的徒弟制)の考え方を、「問題解決」のような認知スキルの習得に適するよう、アレンジしたものなんですね。
わかりやすく言うと、伝統的徒弟制では、職人技や身体的スキルの習得を目的としていて、どちらかというと「背中を見て学べ」で終わっていた部分が多かった。
身体的スキルに優れた職人は、「言語化」したりするのが得意でない場合も多いですから、やむを得ないんですよね。
あと、身体的スキルは、外から見える部分が一定ありますので、「見たらわかる」部分もあるわけですね。
一方で、「認知的徒弟制」は、問題解決や批判的思考などの認知スキルの習得を目的としていて、それに優れた人が範を示しながら進めるスタイルです。
そもそも「問題解決」のような認知スキルは、「見て学ぶ」ことが難しいですよね。だって「頭の中でおこること」ですからね。
ここで重要なのが「言語化」になります。
熟達者(プロ)の頭の中の出来事がある程度言語化されていないと、学べません。
実際には、モデリング、コーチング、足場掛け、といったいくつかの段階を経て、学習者は熟達者(プロ)の思考プロセスを観察し、自らスキルを習得していきます。
実践しつつ学ぶことで、熟達者の「思考回路」「頭脳」の言語化プロセスに学習者も関わり、参加していくわけですね。
認知スキルにおける「暗黙知」を、効率よく学ぶために生み出された手法だと言えるでしょう。
「認知的徒弟制」の手法を用いた指導/学習について、具体的にどのような手順で行っていくのか、見てみましょう。
1980年代から研究が始まっている手法で、目的によってさまざまなアレンジを加えて実践されているようですが、僕は大まかに以下の6つのステップを想定し、実施しています。
①モデルの提示
②観察と助言
③足場づくり
④言語化の支援
⑤省察(内省)の支援
⑥挑戦の支援
上記の一部、特に①②③⑥などは、伝統的な徒弟制でもよく行われていますよね。
認知的徒弟制は、「認知スキル」の習得を目的としているため、④⑤のあたりが非常に重要になります。頭の中で起こっていることは「言語化」しないと観察できないからです。
実際には、④はすべてのプロセスに関与してくると思います。②③④でワンセット、必要に応じて②③④を小刻みにやる、という感じですね。
一つずつ、簡単に解説しましょう。
ここで「指導者」は教える側(プロ・熟達者)、「学習者」は教わる側(学びたい人)を指します。
①モデルの提示
指導者が、実際にそのスキルが必要なタスク(作業)を実践、実演して見せることを指します。発明塾の場合だと、調査や発明を実際にやって見せることになります。
②観察と助言
学習者にも同じタスクや類似のタスクに取り組んでもらい、そのプロセスを指導者が観察し、アドバイスすることを指します。
③足場づくり
学習者が一人立ちできるよう、徐々に支援を少なくしていきながら、学習者に実践してもらうことを指します。補助輪付自転車から、補助輪を外していく感じですね。
④言語化サポート
実践する中で、学習者が考えていることを言葉にするよう促すことを指します。認知的スキルの場合、実際に「頭の中」で何が起こっているのか言語化しないと、実は②の観察すら、ままなりません。
そういう意味では、情報分析や発明(問題解決)のような、特に高度な認知スキルの場合②③④は混然一体となって進むと、僕は考えています。②③における「言語化」の程度が、学習速度を決めるんですよね。
言語化が苦手な方は学習速度が遅くなる可能性が高いので、指導者側に高度な言語化能力が求められます。僕がよく「楠浦さん言語化能力がすごいですね」といわれるのは、そうでないと「言語化が苦手な方」の指導ができないからなんです。
⑤省察(内省)の支援
実施したことを振り返り、さらに言語化を深め、上手く行く手法を自分なりにまとめるよう促すことを指します。④で言語化しておかないと、それを振り返ることができません。人間は、すぐに忘れる生き物だからです。やはり④が肝なんですよね。
発明塾では、その場で、リアルタイムで思考回路を言語化することを義務付けていますが、その理由は「認知的徒弟制」をフル活用して、最短距離で高度なスキル(暗黙知)を学んでもらうため、なんです。
⑥挑戦の支援
学習者が独力で新しい問題を解決するよう促すことを指します。これはわかりやすいですよね。「次、行ってみよー!」ということです(笑)。これは⑤の「省察」で「自分なりに上手く行く方法」を一旦まとめた上で、にしないと、単なる「パワハラ」になります(笑)。準備が出来てない人に次の難しい課題を与えるのは、たぶんダメでしょうね。
これらを、「実践」の中にどう組み込むか、が人材育成において非常に重要なんですね。
これらの6つのステップは、指導者側も学習者側も、よく理解した上で取り組む必要があります。
これらを意識せずに「ただ単にやって見せる」「ただ単に先輩のやり方を見る」「なんとなく上司と一緒に仕事をする」だけでは、何も身につかないか、身についたとしても非常に効率が悪い可能性が高いんです。
何度もいいますが、身体的スキルを取り扱う伝統的徒弟制と違って、認知的スキルは「見てもわからない部分」が多すぎる、というか、ほぼ全てだからです。
スキルアップしたい人にとっての「良い先輩」「良い上司」「指導力のある人」とは、「(その人の)頭の中を徹底的に言語化して説明してくれる人」だと思っておけばよいでしょう(笑)。僕ですね(笑)。
もちろんこれは「認知的徒弟制」の文脈での話です。
今回、認知的徒弟制に関する記事をいくつか読んでみたのですが、結構ひどいのがたくさんありますね(笑)。
企業内教育では、時間とコストがかかりすぎるから、①②③⑥の4つのステップでよい、なんて記事もありました。
でも、上で述べたように④の「言語化」を徹底的に意識しないと、②すら危ういんですよね。そして、⑤の省察なしに、⑥で「次に挑戦!」といったところで、無駄が多い。
特に、「情報分析」「発明」「企画」のような高度な認知スキル(暗黙知)が必要な業務では、④⑤が一番重要だ、といえますので、くれぐれもご注意ください。
そして、もうお分かりだと思いますが、「言語化能力」が低い方を指導者にしないことも、かなり重要です。
あと、「失敗から学んでもらいます」とさらっと書いてる記事も結構ありますが、ある分野の研究では「失敗を反省して学べる人はほとんどいない」とされており、現場で実践しておられる方からも、僕は同じ話を直接聞きました。
そもそも認知的スキルは、個々人がそれまでも持っている知識体系とのすり合わせが必要なので、「自分なりに上手く行く方法」を見つけるしかない、あるいは、そのほうが圧倒的に早いし、心理的ストレスが小さいと、僕は考えています。
これは、発明塾での指導経験にもとづいた、僕の現時点での結論です。
上手くいかなかった方法を振り返ったところで、「すみませんでした」「がんばります」という精神論的で抽象的な言葉は出てくるでしょうが、「で、どうしたらいいの」という「具体論」「解決策」は出てこないんですよね。
注意力不足などに起因したケアレスミスの場合は、有効かもしれませんが、「情報分析」「発明」「企画」のような、創造にかかわる高度な認知スキルには当てはまらないと思います。
あと、「反省」は精神的に相手を追い込むことにもつながりがちで、心理的負荷が非常高いアプローチです。
心理的負荷が高いと、認知的な能力は低下しますので、そういう意味でも良い方法ではないでしょうね。
認知的徒弟制の正しい実践方法は、「言語化を促し(④)ながら一緒に実践して(①)、観察してフィードバックしてあげて(②)、振り返りを挟んで自分なりに上手く行く方法に落とし込んでもらって(⑤)、徐々に支援を減らしながら(③)チャレンジしてもらう(⑥)」という感じかなと思います。
発明塾は、基本的にそうなっています。
基本的に、といっているのは、「学生向け」と初期の「企業内発明塾」ではこの通り実践していたからです。
そしてこれは、弊社がコラムで情報発信している、野中郁次郎先生の知識創造理論における「SECIモデル」とも密接に関連しているんですよね。
一緒に実践して、暗黙知を共有、言語化して、再度、暗黙知に落とし込む、というプロセスは、認知的徒弟制でもぴったり当てはまります。
幸か不幸か現在の「企業内発明塾」は、「必ず結果を出してほしい」というご要望が増えたことにより、「学び」よりも「結果」(新規事業などの企画提案が採用されること)を優先しています。
それでも「気づき」「学び」が非常に多い、という声がありますから、結果を優先している割には、皆さんしっかり理解されているな、という感じです。
結果が自信につながりますから、断片的な知識でも、これでいけるぞという確信をもって使えるんでしょうね。
内容はよくわかったけど自信・確信がないから怖くて実践できない、という状態よりはよいでしょう(笑)。
1回ではとうてい身につかない(プロになれない)高度なスキルを扱っていますので、企業内発明塾を一回経験しただけでは身につかないのは仕方ないでしょう。
これも繰り返しなのですが、「結果が出てない方法は誰も学ぼうとは思わない」ので、最後にしっかり結果を出したうえで、学びたい人には振り返っていただける環境は作っています。
でも、皆さん、結果が出たら安心して、そして何より、疲れきっちゃって、そのまま放置になります(笑)。
振り返りまで、たどり着かない。仕方ないですよね。人間ですから(笑)。
企業内発明塾を振り返るより、社長提案が通った新規事業の企画にもとづいて、次のアクションをすぐに起こして、新規事業をどんどん成功させて欲しいので、僕も振り返りは強制しません。
皆さんの会社の社長さんや役員さんも、多分そう言うでしょう。これはこれで正しいのです。誰も悪くありません。
長くなりましたが、次回は、認知的徒弟制を超える、さらに深い、かつ、効率的な学びの手法を紹介します。
ここが、発明塾の本丸、本質です。
本邦初公開ですので、お見逃しなく(笑)。
今の弊社メンバーでも、ここまで理解している人はほとんどいないかな。
学生向け発明塾の初期メンバーの一部が、辛うじて理解していた、というレベルです。
ただ、企業内発明塾の参加者からは、昔から「発明塾の手法は部下の指導に役立ってます」という声が多数きています。
つまり、発明塾で指導を受ければ、「なんとなく」でしょうが、「部下の指導スキルがアップする」ということなんですね。
その秘訣が、今回の認知的徒弟制と、次回の内容です。
実は認知的徒弟制では、「指導者は正しい」(唯一の正解を持っている)という前提に立つのですが、創造的能力や問題解決が求められる状況では、これが正しくない部分もあります。
「唯一の正しい答えがない状況」あるいは「正しい答えがないかもしれない状況」においても、「全員が即時に学びながら結果を出す」「その場で結果を出し続けながら学ぶ」というのが、発明塾が求めていて、実践している「指導法」「学び方」です。
次回、説明しますね(笑)。
4月22日開講の「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)」では、認知的徒弟制も活用した独自のプログラムで、学びを深めていただきます。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
上記ページから、「詳細資料請求」「説明会動画の視聴」「お申込み」が、それぞれ可能です。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
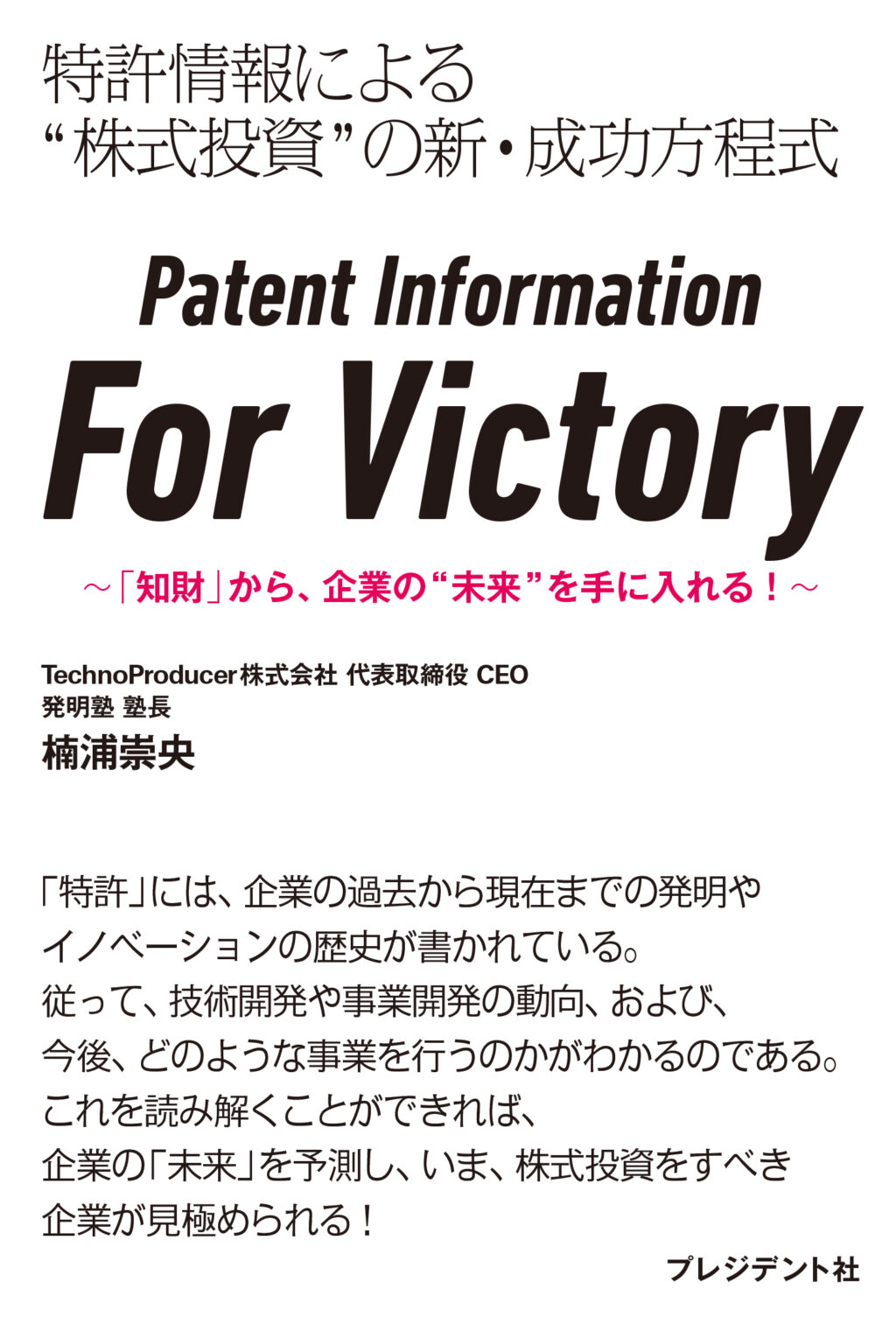
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略