【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は「発明塾が理想とする新規事業の支援」について、認定新規事業サポーターの方と「月額顧問サービス」の中で行った壁打ちのまとめ(お声)紹介、その3です。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)
「支援者」に必要なスキルとして、僕が重視する「動機づけ面接」のお話の、最終回です。
さっそく本題へ。
==ご本人の振り返りメモ(お声)より
※ ご厚意により、全文そのままの掲載を許可いただきました
【7. 企業内発明塾における“動機づけ”とは?】
■ 支援者の意見は「主観の上塗り」になりうる
企業内発明塾で学んだ大切な姿勢の一つに、「提案者に対して支援者の“意見”は不要である」という距離の取り方があります。
これは、提案者が持つ「やりたい、でもやりたくない」という両価的な主観に対して、支援者の主観をさらに重ねてしまうことで、本来の動機をかき消してしまう危険があるためです。支援者の意見は、時に“主観の上塗り”となり、提案者の意思決定を曇らせる可能性があります。■ 情報探索の重要性と当初の違和感
発明塾では、「エッジ情報探索」や「先行特許・事例情報の収集」が推奨されます。最初、私はこれに対して次のような疑問を抱いていました。
「すでにやられていることを掘り起こして何になるのか?
それでは新しいものは生まれないのではないか?」
しかし今では、その意図が明確に理解できるようになってきました。■ 企画は主観だけでは通らない
新規事業の企画は、最終的に決裁者や顧客から“Go”が出なければ前に進まないという現実があります。そこには、提案者の主観だけでなく、支援者の主観を加えたとしても通用しないという明確な限界があります。
たとえ最終判断は“主観”でなされるにしても、その過程では客観的な情報とロジックに基づく構造化が求められます。言い換えれば、「最後に主観は要るが、最初から主観では通らない」ということです。■ 「決断」ができないのは、企画を信じていないから
提案者の中で「やりたい/やりたくない」が揺れ動くのは、その企画を自分自身が信じきれていない状態にあるからです。
提案者が自らの企画を「これはいける」と信じ、決断できていない限り、提案そのものが成立しません。
一方で、決裁者が見たいのは、まさにこの「提案者の決断」なのです。
「提案者はなぜこの企画が“いける”と判断したのか?」
「その判断は企業としての決断と一致しうるか?」この問いに答える必要があります。
■ 決断に必要なのは“事実”と“構造化された思考”
企画を信じるためには、以下のような要素が不可欠です:
・ 5W2Hに基づく客観的な事実
・ 認知バイアスを外した検証済みの思考プロセス
・ その結果として導かれた論理的な構造と判断これらに支えられてはじめて、主観としての「やらせてください」が意味を持つのです。
■ 支援者の本質的な役割とは?
このように整理すると、支援者の役割は次のように定義できます:
提案者が企画を「信じられる状態」に至るための、情報提供者であり、決断プロセスの同伴者であること。
つまり支援者は、提案者の主観を押し付けるのではなく、事実とプロセスの積み上げによって、提案者が自分の決断を形成できるよう支える存在なのです。■ 今回の気づきと今後の検証
この考察は、現時点ではまだ私自身の「仮説」の段階です。今後も発明塾での実践やフィードバックを通じて、この仮説を検証し、深めていきたいと考えています。
(全3回分終了)
==メモ、ここまで
今回も、メモをベースに、私が普段「動機づけ面接」の考えを用いて「新規事業の支援」をどのように行っているか、お話しします。
この記事の内容
長いので、一部だけ引用しておきますね。
(以降同様)
企業内発明塾で学んだ大切な姿勢の一つに、「提案者に対して支援者の“意見”は不要である」という距離の取り方があります。
これは、提案者が持つ「やりたい、でもやりたくない」という両価的な主観に対して、支援者の主観をさらに重ねてしまうことで、本来の動機をかき消してしまう危険があるためです。支援者の意見は、時に“主観の上塗り”となり、提案者の意思決定を曇らせる可能性があります。
僕は、4月に開講した支援者向け発明塾公開講座で、「意見はいらないので手伝ってください」を連呼していました。必要なのは「情報」「ヒント」であって、あなたの意見ではないですよ、ということです。
不十分な情報しかなく、理解が深まっていない提案者に対して、意見を言っても無意味なんですよね。
まず、提案者自身が考えようとしていることについて、「より深く理解してもらう」ことが、第一です。
理解が深まれば、自然と判断できるようになります。
一度判断してもらった上で、「何でそういう判断になったのか(なんでそう思うのか)」を、深堀りし、「だったら、むしろこっちでは?」と、新たな選択肢を創造していくんです。
これが、支援者の役割です。支援者は命令者ではない。ただそれだけの話です。
新規事業の企画は、最終的に決裁者や顧客から“Go”が出なければ前に進まないという現実があります。そこには、提案者の主観だけでなく、支援者の主観を加えたとしても通用しないという明確な限界があります。
たとえ最終判断は“主観”でなされるにしても、その過程では客観的な情報とロジックに基づく構造化が求められます。言い換えれば、「最後に主観は要るが、最初から主観では通らない」ということです。
どんなに経験豊富な支援者でも、支援者の「意見」は、支援者の「主観」に過ぎません。自身の能力や経験を過信して、これを忘れる方が多すぎます。
提案者の「主観」は未熟に見え、自身の「主観」が客観であるかのように思い込んでしまう。怖いですね。
だから、まず「事実」を集める。できるだけ「一次情報」を集める。二次情報には「誰かの意見」が入っているからです。意見ではなく、事実によって、正しい判断に至ってもらう支援をする。
これが支援者です。
この方が書いている通り、客観的にすべてを説明し、証明することは不可能です。そして、その企画を実行するのは、提案者です。
だから、「最後は主観」にならざるを得ない。だからこそ、最初は「客観」を徹底するわけです。そもそも、提案者がアイデアや情報を持ち込んだ時点で、そこには「主観」が含まれています。
育てる以前に、まずそれを解明し理解していくためにも、「客観」が必要なのです。わからないものは、育てられないからです。理解していない人同士がいきなり主観をぶつけあって、良い企画が生まれる気がしません。
企画を信じるためには、以下のような要素が不可欠です:
・ 5W2Hに基づく客観的な事実
・ 認知バイアスを外した検証済みの思考プロセス
・ その結果として導かれた論理的な構造と判断これらに支えられてはじめて、主観としての「やらせてください」が意味を持つのです。
情報が豊富にあるからといって、すべての提案者がすぐに判断できるわけではありません。情報が多すぎて混乱する人。決め方がわからない人。決めるのが怖い人。色々いますね。
いずれにせよ、ある程度情報が集まると、やりたい、と、やりたくない、で揺れ動く、「両価性」が顔を出すステージに入ります。この段階では、「決めないと進まないですよ」ということを伝えると同時に、その人が決めるために必要なものが何か、を見極めて、対処していきます。
「決めるために必要なもの」は、その量を含め、個々人で千差万別です。ただ、大きくは「情報量」と「ロジック」に集約されます。
① 少ない情報から無謀なロジックを立てているので、決められない
② 膨大な情報があって、構造化されていないので、決められない
だいたい、どちらかですね(笑)。
構造化したからと言って、客観的に自明な結論が出るとは限りません。むしろ、出ないほうが多いですね。
だから、最後は「決めてもらう」必要があります。
その人が、「これならいける」と思えて、決めてくれるところまで、支援するしかないのです。
これは、僕がメンバー(部下)との面談でも、いつもやってることです。定期面談では、だいたい「相談」があるのですが、その内容は、まさに上の2つです。
情報が足りずよい選択肢がない、か、選択肢はあるけど決められない、か、いずれかですね。
いずれの場合でも、僕はゼロベースで情報を集め、アイデアを出し、選択肢を整理したうえで、本人に決めてもらいます。決められる、ということは「これならできそうだ」という感触を本人が持っている、ということなので、それで良しとします。
できそうに思えないことは、皆さん途中であきらめてしまうからです。「できそうだな」と思えるところまで、壁打ちをする。説得はしない。説得とは、多くの場合、主観の押し付けですからね。
このように整理すると、支援者の役割は次のように定義できます:
提案者が企画を「信じられる状態」に至るための、情報提供者であり、決断プロセスの同伴者であること。
つまり支援者は、提案者の主観を押し付けるのではなく、事実とプロセスの積み上げによって、提案者が自分の決断を形成できるよう支える存在なのです。
自分で考え、確信犯になって、自分で決めてもらう。これを支援するのが、発明塾における「支援者」です。
多くの上司は、そういう役割を求められていますよね。だから、これはそのまま「良い上司」「良いマネジメント」の技術でもありますね。
新規事業界隈では、よく「伴走」という言葉が使われますが、僕はいまいちこの言葉の意味が理解できずにいました(笑)。「何やねん伴走って」と。伴走は、先導ではないですよね(言葉が違いますので)。
”提案者が企画を「信じられる状態」に至るための、情報提供者であり、決断プロセスの同伴者”
これなんだろうなと、思っています。
皆さんは、どうでしょうか?
「動機づけ面接」の手法を用いた「新規事業の支援」「IPランドスケープ」にご関心がある方は、ぜひお問い合わせください。
動機づけ面接を基礎から学びたい方は、その旨お伝えください。ゼロから指導いたします。
月額顧問サービス
https://www.techno-producer.com/advisory-service/
こちらからお問い合わせください。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
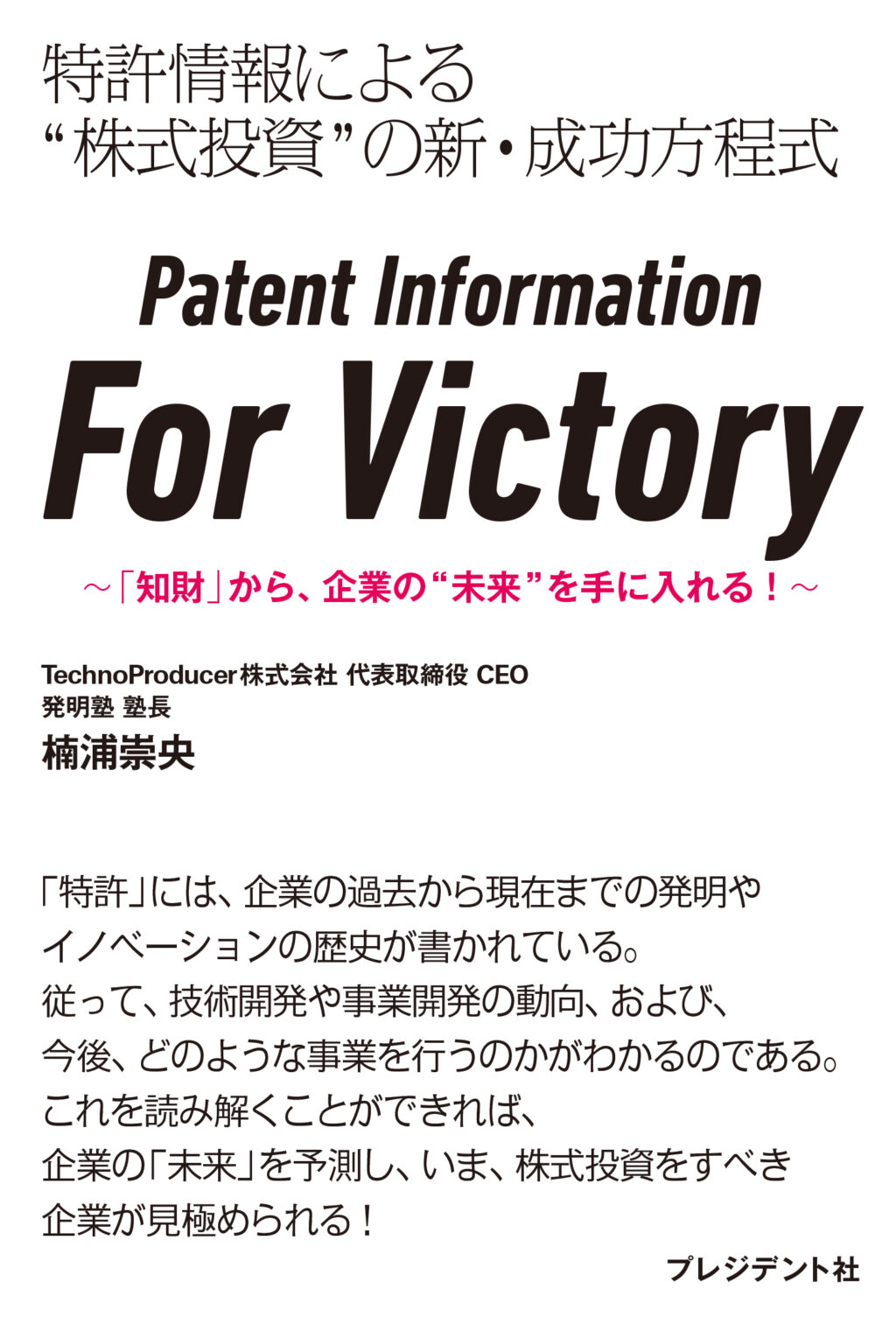
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略