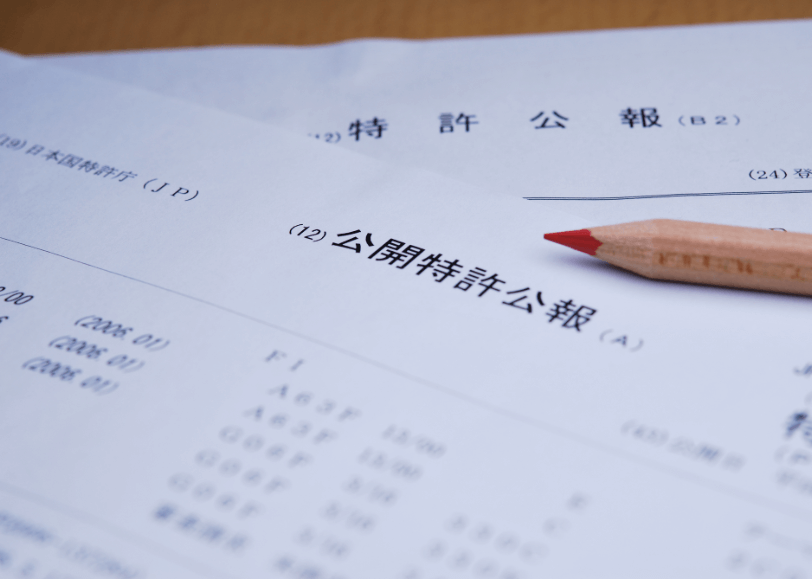特許を「魚の目」で見ると、「技術の流れ」がわかる(ばらばらに読まず、流れを押さえる)
「これは絶対読むべき」という重要な特許があるので、まずそれを読むのがよい(重要な特許を目利きして読む)
技術の流れと「お金の流れ」の交差点に立つことができ、未来が見える(特許情報は未来予測のツール)
特許は「経営」の重要なツールであり、「経営上のオプション」である(特許は、経営と投資に必須)
特許はアライアンスとオープンイノベーションの道具である(特許をうまく「使わせる」戦略もある)
日米の成長著しいAI/IoTベンチャーは、特許を巧みに使って事業を拡大している(特許は事業拡大のツール)