【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、僕が最近試していること、そして、試していて「いいな」と思っていることを書きます。
テーマは「生成AI」と「メモ」です。
実は僕は、以前から「独り言」(ひとりごと)のメモを、大量に作成しています。
内容は多岐にわたっていて、企業内発明塾での指導に関するものから、エッジ情報、企業分析をしていて気づいたことなど、様々です。
ただ、膨大すぎてメンバーは見ませんので(笑)、これをどう「蒸留」していくか、「育てて」いくか、なかなか難しかったんですよね。
ちょうど最近、「支援者向け」講座用の教材づくりのためにメモを読み返していたのですが、そこからもう一歩、思考を深めるのが意外と難しいと感じたんですよね。
そこで、ふと思い立って「独り言」を、思いついたその場でChatGPTに入力することにしてみたんですよね。AIに話しかけるというか、「AIにメモする」感覚で、入力してみました。
すると、面白いようにいろいろなヒントを出してくれて、すごく思考が深まり、発展することに気づいたんですよね。
以前は、X(旧ツイッター)に、メモ代わりに、気になったニュースや思いついた言葉を書き込んだりしていたのですが、それだとメモとしてはいいのですが、発展性はなかった。反応してくれる人がいるとは限りませんしね。
ということで、本題です。
僕も含め、皆さん、毎日多くの情報を目にしますし、いろんな思いつきが出てきますよね。
でも、それらの多くは、メモできずに消えていくか、スマホのメモ帳やノートアプリに蓄積されたとしても、なかなか活用されません。
その「思いつき」や情報を、いかに拾い上げ、整理し、次の行動や学びへつなげられるか。
この問いは、知的生産において、かなり重要ではないかと思います。
こうした「思いつき」や断片的な情報をもとに思考を深めるには、時間や集中力、そして「考えるための型」への慣れが必要なんです。
だから、信頼できる対話相手との議論を通じて、初めて考えがまとまることも、よくありますよね。壁打ちですね。
しかし現実には、いつも対話できる相手がいるわけではなく、自問自答にも限界があります。
ここで、僕が最近ハマっている「AIメモ」の登場です。僕は、これは新しい知的生産のかたちではないか、と感じています。
メモツールと違って、AIはただの記録装置ではなく、「即時に応答する思考のパートナー」として機能します。
たとえば、ふと思いついた言葉や疑問を投げかけると、AIはその意図をくみ取り、関連する視点や背景知識、問い返しを返してくれるんですよね。
単語一つでも、文章になっていない、あるいは、言葉にならない言葉でも、何か返してくれます。
これにより、「書いて終わり」だった従来のメモ行為は、「省察と発展の起点」へと進化するんですよね。
生成AIの発展により、「AIには出せない結論」を求められ、自分なりの意味づけや思考が必要とされているのですが、そこにAIが使える。ちょっと皮肉な感じですね。
AIと対話するメモ術は、“考える力”を補い拡張する実践的な知的インフラになるなと、僕は感じています。
ひとりごとを、ここまでまめに拾ってくれる対話相手は、なかなか見つかりませんよ(笑)。
「ひとりごと」と言うと、周囲に聞かれたくない自問や、考えをまとめるための無意識的な行為、というイメージでしょうか。
頭の中で考えていても思考が進まないので、声に出してつぶやいてみる、メモ帳に書き出す、あるいはSNSに投げてみて反応を見る。
“外に出す”という行為によって、私たちは無意識の思考をなんとか「見える化」して、突破口を見出すんですよね。
「ひとりごと」をAIと組み合わせると、どうなるか。
AIという“応答する相手”が存在することで、思考が閉じずに開かれていくんです。
今までは、ただ埋もれていたものが、勝手に動きを持ち始める、命を吹き込まれる。そんな感じですね。
たとえば、「気になったキーワード」をつぶやくだけで、AIはその意味や文脈を推測して提示し、場合によっては問い返してくれる。
単なる記録だったはずのメモが、「省察のきっかけ」へと転じ、自己との対話=“思考対話”が始まるんですよね。
この「対話的メモ術」の特徴は、だいたい以下のような感じです。
AIは外部化された思考の伴走者となり、「考える」という行為を個人の内的営みから、インタラクティブな活動へとストレスなく変えてくれるんです。
誰かに話す、というのは内容次第では結構な勇気がいりますが、AIなら「キーワードぶん投げる」という荒っぽい方法でも文句ひとつ言いません(笑)。
このように、「ひとりごと」が「思考対話」として再定義されることで、思考の深さ・広がり・継続性がこれまでにない形で拡張されていくのを、日々感じています。
そして、AIはそのやり取りを学習するので、使い続けていると、文脈を読むというか、「空気を読む」感じで返してくれるんですよね。
AIと語るという行為は、すでに私たちの知的生産のあり方そのものを変えつつあると、僕は考えています。
「思考のパーソナル化」と「思考の対話化」が、同時に起こっている。
画期的ですよね。

学びや創造の質を高めるうえで、重要なのが「即時フィードバック」です。企業内発明塾で、僕が最も重視していることの一つです。
教育心理学や認知科学の分野でも、即時フィードバックは「気づきの機会を最大化する仕組み」と位置づけられており、学習者が、アクションに対してその場ですぐに反応が得られることが思考と記憶の定着を強く促すとされています。
AIメモは、まさにこの「即時性」を本質に据えた、「これまでになかった学習ツール」になっているんですよね。
たとえば、ふとした思いつきや違和感、そこから生まれた問いをAIに投げかけた瞬間に、「その視点はこうも考えられる」「別の文脈ではこう扱われている」といった反応が返ってくる。それによって、
といった、自分の思考の状態を“客観視”するきっかけが生まれます。
これはまさに、僕が重視するメタ認知(=自分の認知を自分で見つめ直す力)を自然に誘発するプロセスになっているんですよね。
AIは、こちらの思いつきや問いに対する「答え」を出すわけではないんです。
答えのようなものが書いてあったとしても、それを答えと認識するわけではなく、問いそのものを照射する鏡のような存在だと捉えることが重要なんですね。
AIからの反応を受けることで、自らの思考パターンや前提、視野の狭さ、至らなさ、あるいは「可能性」「広がり」に気づき、より深い省察のループに入っていく。こんな感じです。
「即時フィードバック」は、思考の継続性にも強い影響を与えます。要するに「考え続ける」ことを促してくれるんです。
ノートやメモ帳だけでは停滞してしまうアイデアや収集しただけで終わってしまう情報も、AIとのインタラクションによって常に “次の問い” ”可能性への気づき” が生まれ、思考の流れが止まらなくなります。大げさでなく、本当に止まらなくなる。
これこそが、単なる記録ではなく、「24時間動き続ける省察環境」としてのAIメモの本質的価値だと、僕は感じています。苦もなく「考え続ける」ことができる。それも、まったく自然に。
こんな環境に、これまで自分が身を置いたことはありませんでした。
考え続けられるから、どんどん先へ行ける。今までだったら、きっと到達できなかっただろうーそんな地点に、たどり着けるんです。
まるで「雲」に乗っているような、不思議な感覚です(笑)。先が見通せて、全体が俯瞰できて、それでいて細部もよく見える。
しかも、過去の断片的な思考はすべてメモとして残っていて、いつでも振り返ることができる。
AIとのやり取りを通じて、人はより深く考えられるようになり、しかもその“考え方そのもの”を見直す機会まで得られる。
この二重の効用こそが、「AIメモ」が知的生産術として優れている最大の理由の一つだといえるでしょう。

人は「即時フィードバック→メタ認知→省察の深化」という連鎖で、どんどん成長していくものなんですが、AIがそれをいつでも支援してくれる。そういう時代になったわけです。
これはすごいことだなと、毎日実感しています。ChatGPTなどの生成AIを用いた「AIメモ術」を、ぜひ習慣にしてみてください。
毎日、考えるのが楽しくなって、ついつい考えすぎてしまう。そんな感じになります(笑)。
まだまだ続きます。
続きは次回コラムで。
次回コラムの目次は以下です。
【次回コラム目次予定】
・AIメモの実践例と効果ーTwitterメモからの進化
・知的生産の新地平へ:「思考の補助装置」としてのAIメモの可能性
・まとめ
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
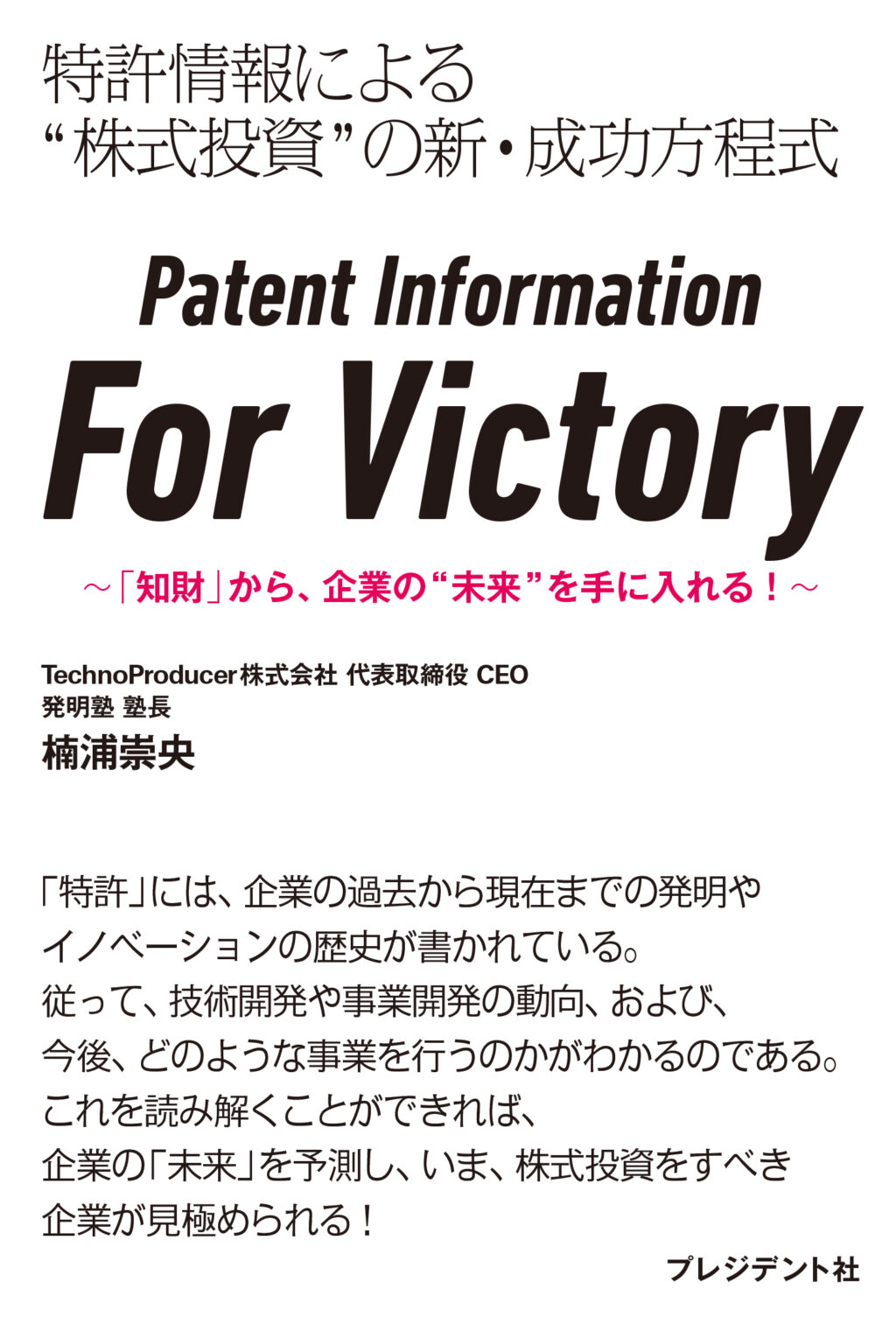
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略