「発明塾」塾長の楠浦です。
今日も、2025年4月に開講する「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾 公開講座)」に関連する内容を、紹介していきます。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
上記ページから、「詳細資料請求」「説明会動画の視聴」「お申込み」が、それぞれ可能です。
「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾 公開講座)」では、支援者の方に発明塾の手法を学んでいただくだけでなく、「学び方」「指導法」まで学んでいただけたらよいな、と考えております。すでにお申し込みの受付を開始しております。
先着10名様までの募集となりますので、ぜひ参加したい、という方は早めにお申し込みをお願いします。
前回は、「プロ」「仕事がデキる人」になるための「暗黙知」獲得の具体的手法の1つである、「実践共同体」「正統的周辺参加」のお話をしました。
・正統的周辺参加と認知的徒弟制の違いは、知識を「師弟関係」ではなく「実践共同体」での共同行動を通じて獲得していく点にある。
・正統的周辺参加の理論では、学習は「状況に埋め込まれたもの」であって、実際の状況を通じてしか学べないものがある、と考える。
・正統的周辺参加において、初学者も実践共同体の正統なメンバーとして扱われ、周辺的な役割から徐々に主体的に参加し、自ら知識を生み出していく。
・発明塾でも、正統的周辺参加の理論を実践しており、気づきを得た人が他者に教えることで、全員が学ぶ仕組みを構築している。
今回は、「唯一の正しい答えがない」あるいは「正しい答えがないかもしれない」問題に取り組みながら学ぶことが、いかに重要であるか、についてお話をします。
学習が状況に埋め込まれたものであるとすると、その状況が実際のものでないと学べない部分があるわけですね。
その場合、「状況」が実際に起こるものでないと、学習の効果は低いわけですから、今から説明する「真正性の高い問題」に取り組む、というのは非常に重要な視点になります。
この記事の内容
多くの社会人が実際の業務で直面する、問題解決や創造的スキルのような認知的スキルが必要とされる場面は、「唯一の正しい答えがない状況」あるいは「正しい答えがないかもしれない状況」であると考えられます。
少なくとも、「答えがあらかじめわかっている(決まっている)」ことは、業務ではほとんど無いでしょう。
要するに、練習ではなく実戦であり、しかも、同じ問題に遭遇したことがない、という状況なわけです。
こういった情報に対応できるスキルをを身につけるには、「真正性の高い問題(Authentic Problem)」に取り組むしかない、とされています。
真正性の高い問題(Authentic Problem)というのは教育学の用語で、わかりやすく言うと「実際に起こっている(起こりうる)問題」ということです。
まぁ、要するに「実戦でしか身につかないものがありますよ」というだけの話です。
近年の教育学の成果として、「学習の転移」が思っていたほど起きないことが示されています。
学習の転移とは、ある場面で学んだ知識やスキルを、別の場面で活かし結果を出すことを指します。
要するに「学んだことを応用できるか?」ということです。例題で学んだら、類似の他の問題が解ける、というイメージでOKです。
これが、実はあまり起きないことがわかってきているんですよね。
「応用」する能力って、それ自体が結構高度なスキルだということでしょう。
そうなると、必要最低限の知識を身につけた後は、「実戦」「実践」しかない、という結論になります。仮にトレーニングを行うとしても、限りなく実戦・実践に近い状況で行うしかない、ということです。
特に今後は、認知的スキルが必要とされる問題であっても、簡単なものはAIが解決してくれるようになりますので、ますますこの「実践」が重要になります。
実践共同体で、正統的周辺参加により学びを深めていく場合、メンバー間での相互作用から知識を生み出し、習得していきます。
真正性の高い問題であれば、ベテランであっても経験していない状況に遭遇する可能性があります。
これが結構重要なんですね。
ベテランが経験したことがない問題について、初学者が新たな解決法(知識)を生み出す可能性もあります。
「師弟」や「レベル」のようなマクロの物差しでは捉えられない、「学び合う」関係が生まれるんですよね。
ミクロには、全員がなにか優れた点を持っていて、それが他者にとって参考になり支援になる、ということです。
「素人発想」という言葉がありますが、近いイメージだと思います。
これが実践的共同体の醍醐味であり、本質の一つだと僕は考えています。
真正性が低い、すでに答えがわかっている問題に取り組む場合、教える側と教わる側が固定され、そこで「教える側が知っている答えに導く」ような、ある種の誘導尋問(笑)が起きがちです。
これは「導かれた発見」(Guided Discovery)と呼ばれます。これでは、誰も何も学べないんですよね。
真正性の高い問題、答えを誰も知らない問題に取り組むことで、全員が成長できる。
誰かが知っていることだけでなく、誰も知らなかったことも学べる。
全体として非常に効率がいいんですよね。
実践共同体で真正性の高い問題に取り組み学ぶことのメリットは、他にもあります。
結果を出しながら学ぶ、という意味で、全員の自己効能感を高めることができます。
一人ではできないことでも、「共同体」としてみんなで行えば、できますからね。
また、突出した指導者が不要という点も、メリットは大きいでしょうね。
指導者がいて、教わる、という構造ではないからです。
実践しながら、未解決の問題を解決できる知識を生み出していく、という意味では、企業での実践や問題解決を学ぶのに向いた手法だと、僕は考えています。
実際、学生版発明塾では、早い段階で「楠浦さんがいなくても学べる環境を作る」ことを一つの目標にして、「認知的徒弟制」を脱却して「正統的周辺参加」「実践共同体」へ移行し、大きな成果をあげてきました。
さらに楠浦も、そこに加わることで、彼らからの気づきを得て大きく成長できた、というおまけつきです(笑)。
組織が、規模と能力の両方の点であるレベルより上に行こうとするなら、「実践共同体」「正統的周辺参加」しかないと思います。
僕は大学で、発明について講義を行うことがよくあります。
その際、学生さんに「熟達者の知識は相互に関連付けされ体系化されているため、部分的に教えることは不可能」だ、と話しています。
多くの学生さんは、受験勉強などを通じて「形式知」を学ぶことが「学習」だと思い込んでいますので、意外に感じるようです。
一方で、学習に対して感じていた違和感が解消された、という学生さんもいます。
特に、適応的で分析的なスキルは、熟達者であってもその場にならないと再現できない部分があります。
これは、認知スキルの指導や習得を著しく困難なものにしていると、僕は思っています。
しかし、熟達者の認知スキルは、そもそもある特定の状況の中で挑戦を繰り返し、熟達者自身が生み出した知識なので、同じような「状況」を共有することでしか、理解できない部分が多いでしょう。
しかも、大半が頭の中で起こることであり、「観察」してもわからないのが認知スキルの特徴ですので、「一緒に挑戦する」ことでしか共有ができないわけです。
実践共同体の必要性は、明白ですね。
4月22日開講の「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)」では、「成果を目指さない」という制約はあるが、実践共同体に近い運営を目指したいと考えています。
企業で、発明塾のような取り組みを継続するには、「実践共同体」「正統的周辺参加」しかないからです。
実際には、認知的徒弟制と正統的周辺参加のハイブリッドになると考えています。
すでに誰かが突出したスキルを持っている領域では、認知的徒弟制に近い「指導」が行われる場面もあるが、トータルではそれらが「学び合い」として「状況に埋め込まれた形」で自然発生し、全員のレベルが上がる。
学生向け発明塾が、まさにこういう感じでしたので、それに近い「場」を作っていきたいと考えています。
皆さまのご参加を、お待ちしています。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
上記ページから、「詳細資料請求」「説明会動画の視聴」「お申込み」が、それぞれ可能です。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
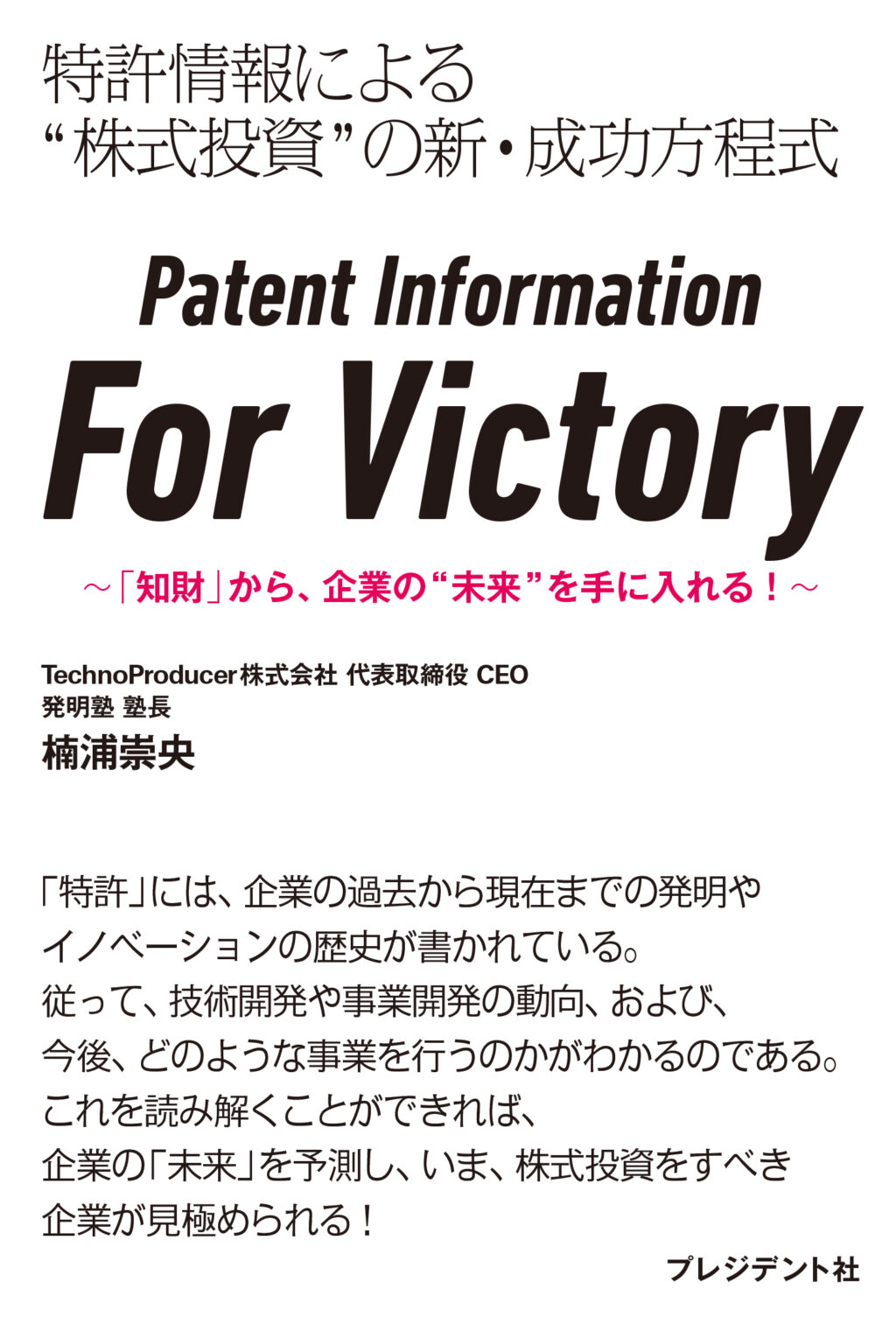
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略