「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、2024年11月に開催された「億の近道」の投資家向けイベントの空き時間に、ある「投資アナリスト」の方にお話しした内容を、ご紹介します。
投資に限らず、「アナリスト」や「新規事業」「研究・開発」を担当する方など、「認知負荷が高く、適応的で分析的な業務」に携わる方は、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
要するに、「暗黙知」領域の話です。
ぜひ、最後までお読みください。
それでは本題です。
この記事の内容
すでに皆さん、毎日のように「生成AI」を使っておられると思います。
質問すれば、瞬時に「それらしい」答えを返してくれ、その根拠も示してくれる。
もはや、下手なアシスタントや部下、後輩より、使えるやつですね(笑)。
以前の配信で、「人を育てるよりAIを育てたほうが安い時代」だという話をしました。
また、この文脈で「簡単な業務がAIに代替されることで、入門的な業務がなくなって経験が積みづらい」時代になっていく、というお話も、各所でしています。
僕の周りでも、すでにそうなっている気がします。
「これ調べといて」「これまとめといて」「これやっといて」的な業務は、徐々にAIに任せるのが得策になっていくわけです。
ただ、そうは言っても、そういう仕事が「膨大」にあると、やはり人間が介在する余地があるでしょう。
「認知負荷が高い」とは、そういうことですね。
実際、企業内発明塾を受講された方が先日、「楠浦さんは、形式知化が進みすぎていて、それ自体が膨大な量になって、もはや私には使いこなせません(笑)」と仰っていました。
「膨大な形式知」の使いこなしは、「認知負荷が高い」わけです。
形式知とは、簡単に言うと「言葉になっている知識」です。
対になる言葉は「暗黙知」ですね。「言葉になっていない」「言葉にできない」知識だ、と理解いただいてOKです。
膨大な形式知を使いこなすには、「暗黙知」が必要。
テキストを丸暗記して当てはめる、少しアレンジする、はAIでオッケー。
目の前で時々刻々変わっていく状況に、膨大な形式知を当てはめていくには、AIだけでなく、人も必要。
そんな感じですね。
僕が発明塾で「その場で答えを出す」「その場で決める」ことを重視しているのは、そこに人の存在理由がある、と考えているからです。
情報がない中で、仮説的に議論を進めていくスピードは、やはり「人」ならではのものでしょう。
一方、その検証は、あとでAIにやらせてもよいわけです。
繰り返しですが、こういう「検証」作業も、以前なら「見習い」「新任」担当者の仕事だったわけです。
僕も何度か、「上司が設計した結果の検証」をやらされました。
それで「設計に必要な思考回路」(暗黙知)が理解できるんですよね。
ちなみに、AIも学習初期は丸暗記で、いわゆる「過学習」状態だとされています。
タスクをこなしながらチューニングされて、「ええ感じ」になっていくのだとしたら、まさに「初心者が中級者になる過程」をAIもたどっているわけです。
初心者が学習機会を奪われている、とも言えますね。
広い意味でAIに仕事は奪われない、と僕は考えているのですが、特にエントリー層の学習機会は、どんどん奪われている気がします。
僕も、以前ほど人に仕事を教えなくなったというか、教えたいから簡単な仕事を任せたいんだけど、残念ながらその手の仕事はAIの方が圧倒的に早いし、深夜まで付き合ってくれるし、何度でも答えてくれるので、、、という状況が生まれています。
初心者が「どう学ぶか」が問われる時代になっている気がします。
もちろん、僕も常に何かの初心者なわけですから、同じことを意識して、学んでいます。
次の話題に行きます。
僕が意識しているのは、「いかに良い経験を、短期間に、長時間積むか」です。
短期間、はいったん置いておきましょう。
良い経験を、長時間積む、これをどうするか、ですね。
生成AI登場以降、僕は、いきなり一流の人に教えを乞うことに決めました。
回り道をしている時間がないというのもありますが、AI相手に仕事していけば身につくレベルのことはAIでよい時代になった、と理解しました。
だから、一気に一流の方がいる場に飛び込むことにしています。
実際、僕は「動機づけ面接」という心理療法のシニアリーダーの資格を持っているのですが、それは、「第一人者」の先生のワークショップへ参加申し込みするところから始まりました。
申し込み後、先生の著書やその著書の引用文献(原典)を買い集めて一気に読み、AIの助けも借りてシミュレーションも行って、半年かけてワークショップに参加しました。
事前にAIで予習していた方がどれぐらいいらっしゃったか不明ですが、臨床経験がない僕がそれなりにワークショップで実務に近いケースをこなせたのは、予習の成果だと思っています。
「動機づけ面接」自体も、AI化を進める動きがあります。
このAIは医療機器になるでしょうから、まだまだ先は長いと思いますが、面白い動きです。
このように、暗黙知が占める部分が大きい分野では、「事前学習」「AIとのスパーリング」を経て、「その道の第一人者」のもとへ飛び込む、という学習経路が非常に効率が良いことを、身を持って体験しました。
ちなみに、その後のフォローアップでもAIが使えるか試したのですが、第一人者に指導を受けて、ある程度マスターした後だと、AIでは全く足りないと感じました。
というか、違和感しかない感じです(笑)。
レベルが高い場所での、継続的な学習や修練が必要なんでしょうね。
日々実践し、独自の実践知を積み上げていくしかない領域に入ったということです。
僕の場合、企業内発明塾で使っているテクニックの一部には、「動機づけ面接」に着想を得たものもありますので、実践がトレーニングになって、新たな知を生み出している感じです。
結局、仕事をするのが最も良い訓練なんですよね。
前置きが長かったのですが、僕が投資アナリストの方にお話ししたのは、ここからです(笑)。
20年前の話になりますが、コマツ時代の上司であった新規事業部門のトップ(事業部長)が、僕に教えてくれた「究極のOJT」法があります。
大学生にも教えていたので、メモが残っています。
「発明塾」へようこそ!: 「計画的に勉強する”仕掛け”をつくる」~塾長の部屋(49)
https://edison-univ.blogspot.com/2013/09/blog-post_8.html?m=1#gsc.tab=0
詳細は読んでいただくとして、エッセンスと補足を書いておきます。
コマツ時代の上司の教えは、シンプルです。
彼は、「俺は設計者ではないから、楠浦には何も教えられない」と断言しました(笑)。
良い上司です。
適当にごまかされたりしなかったので、とてもありがたかったですね。
教えているふりをされても困るからです。
時間の無駄ですからね。
彼曰く、「学び方」を教える、とのこと。
ポイントは、以下の3つ。
「目標とする設計者を決めて」
「その人のスキルを因数分解し」
「それぞれに対して、今何%で、毎月何%に向上させていくのか」
これを、毎月の面談で報告せよ、といわれたんですね。
ちょうど隣の席に、建設機械の設計歴20年ぐらいの、素晴らしい先輩がいたのでその人を目標にしました。
僕は、専用の面談ノートに言われた通りのことを書いて、毎月説明していました。
やってみたらわかりますが、だいたい最初は30%にしとくんですよね。
自信はないのですが。
では、なぜ、自信がないのか。これが大事なんです。
それは、「自分の実力も、相手の実力も、わからないから」です。
要するに、最初は「解像度がめちゃくちゃ低い」んですね。
だから、上司への報告もいい加減なもんです。
重要なのはここからです。
毎月、「何がどう近づいているか」も聞かれます。
上司には多分わからないけど、説明します。
そして毎月、数字の上では10%ぐらいずつ、どのスキルも先輩に近づいていきます。
70%をつけたところで、気づきます。
「あー、俺まだ全然、10%も行ってないわ」(笑)。
要するに、「近づいたことで見える」「解像度があがる」わけですね。
で、本当の勝負はここからです。
ある程度近づいたはず、というところで、「本当の差」「本当に習得を目指すべきスキルと、そのレベル」が見えてくるので、改めて目標と計画を立て直します。
すでに3、4か月経過しているのですが、実はここがスタート地点なんですね。
勘のいい方は気づいたと思いますが、あと3か月ぐらいすると、さらに解像度があがって、「見えてなかったものが見えて」来ます。
これを何度か繰り返すと、「100%ではないけど、結構先輩に近づいたぞ」「後は自分で、自分なりに学んでいけそう」という状態になります。
こういう「学び方」を教わったので、コマツ時代の事業部長には、大変感謝しています。
その後、アメリカで工場長をされるなど、案の定出世されています。
指導力を高く評価されてのお話だろうと、思ってます。流石です。
「AI時代」のスキルアップについて、現時点での僕の結論は、こうなっています。
以下、楠浦メモと称して、発明塾生にいつも共有している「独り言」から抜粋。
これまで以上に「経験」をどう積むか、が重要になる。
経験を「質」と「時間」に分けるとして、質が同じなら「時間」がモノをいう。
時間を短くするには「質」を上げるしかない。
そのために、「第一人者にいきなり教えを乞う」という方法もある。
教えをモノにするには、「解像度」がモノを言う。
「観察」できないものは、身につけられないから。
解像度を上げるための、準備をどうするか。
AIを使ってシミュレーション、模擬演習をするのも一つ。
「目標」にどれだけ近づいているか、目標がそもそも「見えて」いるか、定期的に確認する。
自分も、目標も見えていなければ、スキルアップは難しい。
ここまで、質の高い経験を積むためにできることを挙げた。
では、実際に「今」、質の高い経験を詰めているか、どう判断するか。
繰り返しだが、測定できないことは改善できない。
何か月もの間、質の低い経験をして、結果が出ませんでした、何も身についていません、では無駄が多すぎる。
経験の質をどう定義するかはいろんな議論があるが、感覚として「濃い時間」を過ごせているか、という、その場における主観的な判断になるだろう。
結果でしか評価できないのでリアルタイムモニターは難しい。
そして、Aさんにとって良いものがBさんに良いとは限らない。
そこまでの経験や暗黙知に依存する。
結局、「良い経験、質の高い経験を(短い期間で)長い時間積める環境を、自分なりにどう作るか」に帰着する。
発明塾が、「徒弟制度」的なプログラムになっていることと、極めて密度の濃いものになっている(とみなさんが認めている)のは、これが理由。
「経験でしか身につかない領域」に絞り込んで、早く(短い期間で)経験を積むことで、「成長」「成果」が実感できる。
「忘却曲線」に打ち勝ってスキルアップするために、「できるだけ短い期間」で経験を積みたい。
のんびりやっても、忘れていくだけで、積みあがっていかない。
むしろ、経験の「垂れ流し」になる。
実感できるほどのスキルアップは難しく、途中で挫折してしまうだろう。
「複利効果」を使って、一気に結果を出したい。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
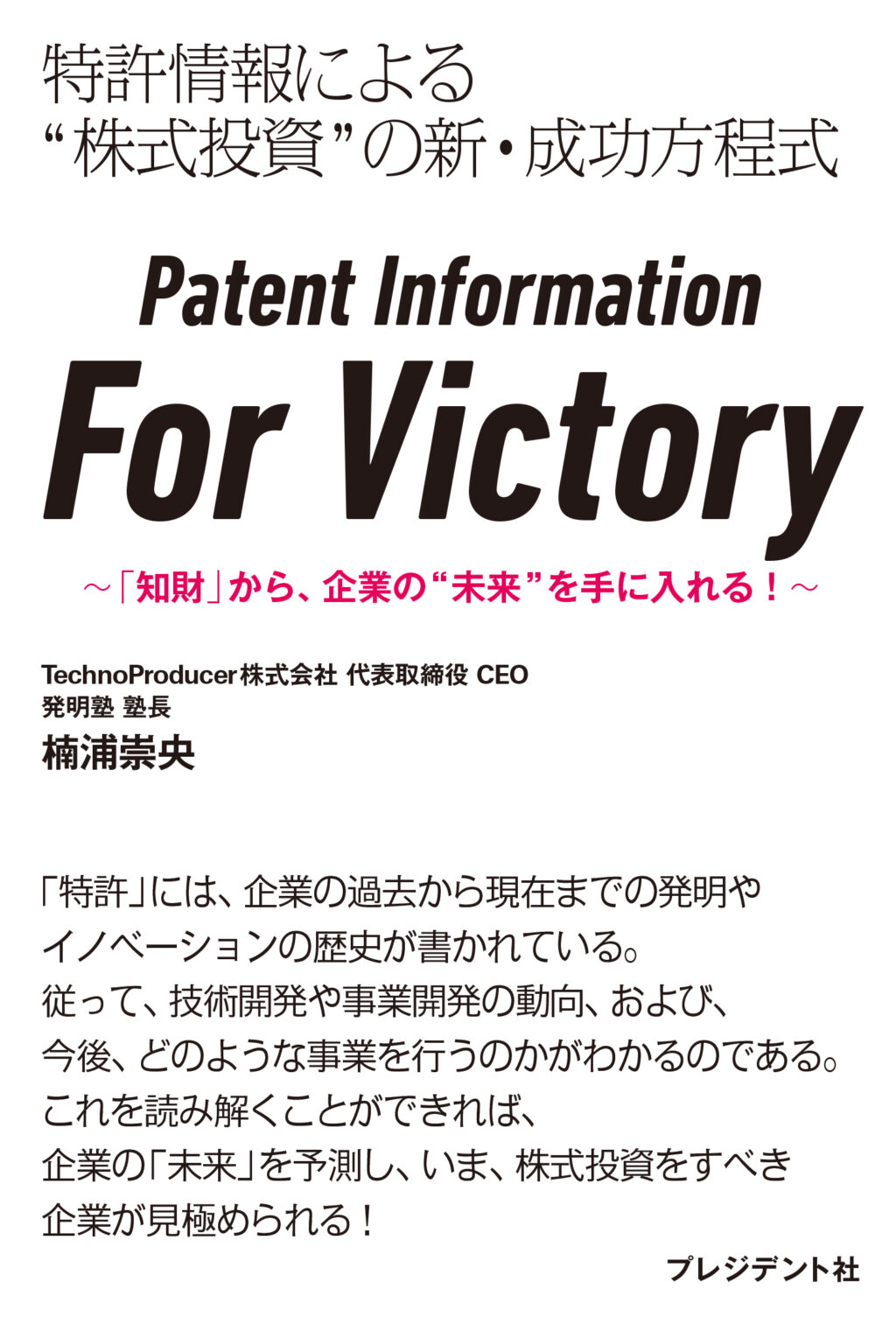
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略