【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、イベント参加報告を兼ねて、「組織の活性化」「人材の活性化」「組織と人の成長」に関するお話をします。
弊社の実働支援サービス「企業内発明塾」の一つのテーマでもありますからね。
2025年5月24日(土)に、日立製作所の有志によるコミュニティ「フラットチャンネル」の5周年記念イベントで「組織活性化」についてのパネルディスカッションに登壇しました。
「フラットチャンネル」は、日立製作所の方だけでなく、他企業の方も参加できる、まさにいろいろな意味で「ふらっと」「フラット」なイベントで、当日、いろいろな企業の方とお話しさせていただきました。関係者の皆様、ありがとうございました。
過去、何度か講師として登壇させていただきましたが、すべてリモートだったため、初めて日立製作所の横浜事業所を訪問。場所はJR戸塚駅すぐ。緑も多く、戸塚駅前とは信じられない広さでした。
個人的な萌えポイント(笑)は、知財部門の行き先案内板?と呼ぶのかな、こっちが知財部ですよ、という綺麗な看板が、事業所内にあったこと。当たり前なのですが、時代ですね。
さて、パネルディスカッションは、大変好評でした。
40分なので「問い」は3つ。
Q1:組織が活性化している状態とは?
Q2:それって会社都合? 社員のため?
Q3:フラットチャンネルへ、今後の活動提案(活性化文脈でということだと理解)
僕の回答を紹介しておきます
この記事の内容
実は、聞かれるまであまり考えたことがなかったのですが(笑)、自分がどういう基準で会社を経営しているかといえば、ズバリ、組織として「結果が出ていること」だろうなと。これは、当日お話ししました。
その後、AIと対話していて、もう一つ「成長期待」というワードが出てきました。
「結果が出る」とわかったので、自分たちが正しい努力をしている、成長している、と感じられる。成功体験ですね。そうすると、「やればできるじゃん」「もっとやってみよう」「もっとできるのでは?」になるんですよね。
一度この状態になると、あとは「成長期待」で活性化していきます。この話は、後で取りあげます。
「結果が出ている」の話に戻りましょう。
結果が出ているから活性化しているとも限らないので、必要十分ではないのでしょうが、でも、中長期的に考えると、やはり継続的に結果が出ているということは活性化しているということなんだろうと思っています。
この「継続的に」のところに、「成長期待」の話が出て来るわけですね。
大事なことは「組織として」結果が出ている、というところだと思っています。各自がそれなりに頑張ってても、かみ合ってなければ意味がないですからね。
でも各自、「個人としての成長・成功」も体感したい。ここが難しいところかもしれませんね。
懇親会では、「楠浦さんもよくご存じのA社なんかは、結果は出てますがあれって活性化しているといえるんですかね?」などという、具体論の突っ込んだお話がありました。とてもよく勉強(=企業分析)していらっしゃる個人投資家の方からのご質問でした。
これは非常に盛り上がったのですが、ここには書けないので(笑)、とりあえず次の問いへ。
組織・人材の話だと明示されているので、「組織の活性化」「人材の活性化」に書き換えています。こちらは、僕の中ではすごく明確です。
「会社の話なので、会社都合です。ただ、会社や組織は、メンバー、個々人の都合を無視しては動かないので、メンバーの都合を最大限考慮した上での、会社都合・組織都合、ということになる」
これに尽きます。
個々人の能力を最大限活かしていくには、これ以外の選択肢はないでしょうね。
全体として、やるべきことは会社の都合というか、会社として掲げていて、それを理解してコミットしたうえで個々人が会社に入ってくるし、存在している。だから、会社都合であることは間違いないし、そこに個々人もあらかじめコミットしている。
だけど、コミットしているからと言って会社や組織の都合で人が「能力を発揮するか」といえば、そんなに甘くはない。
主体性というか、自分ごととしてやり切って結果につなげてもらうには、個々人の都合をどこまで取り入れられるか、それをさらなる強みや資産として生かせるか、が重要だということです。
往々にして会社が言う「やるべきこと」が変わるのも、難しさですね。
これについては、僕はAIメモを駆使することも含め、「知識」「情報」を民主化することを徹底しています。そうすると「権限」も移行できる。自分ごととは、そういうことですね。知識と情報がない中で権限だけおろしても間違える。
これまでは、「情報」は共有できても(例:データベースなど)、「知識」(頭脳)の共有は難しかった。こちらは膨大な経験と情報をもとに、日夜いろいろなことを考えていますが、メンバー全員がそうかというとそんなわけはない。また、それを強制もできない。
ただ、AIメモを使えば「楠浦さんが今何をどこまで考えているか」が瞬時に共有できて、その続きもそのままAIとの対話で考えられる。「知識」(頭脳)も瞬時に共有できる時代になった。これで、権限も下せるようになったわけです。
活性化の前提は、「情報」「知識」「権限」が現場に一体で降りていることだと、僕は思ってます。どれが欠けても、ダメです。
生成AIによってはじめて、組織の本当の活性化が可能になったと、僕は考えています。
これも、僕の中では明確です。「結果を可視化する」ことに尽きるんですよね。
結果が出ている、つまり、「自分たちが正しいことをやっている」ことがわかれば、多くの人は、もっと頑張ろうと思います。なんか間違っているとわかれば、何とかしようと思う。
だから、参加者の方から、もっとフィードバックがあればよいですね、というか、お願いします、と言っておきました(笑)。こういう結果につながったよ、新規事業が生まれたよ、商品が売れたよ、いい出会いになってよく飲みに行く、何でもいいです。
ささいなことでもよいので、多くの「結果」「成果」が生まれているとわかれば、今後何をどうしたらいいか、自然に見えてきます。
測定できないものは科学できない。だから議論もできない。
僕は技術者なので、そういうシンプルな考え方でやっています。
まず、測る。そしてそれを見る、見せる、共有する。
実は、多くの人は、測定結果を見れば、なにがしか動き出すんですよね。
僕がAIと行った対話の結論を、紹介しておきます。
「組織・人材の活性化とは単なる “雰囲気” づくりではなく、組織・個人・未来の交点の設計にあるのでは?」
ちょっとわかりづらいですね(笑)。もう少しブレークダウンしておきましょう。
一人でできることは一人で趣味でやればいいわけであって(笑)、やはり、「仲間」「会社のブランド」「設備」「資金」など、会社や組織の資産を活用して自分の成長や成果を実現したい、というのが、企業や組織における個々人の動機でしょうね。
会社や組織は、自分が死んでも存続しますので、「自分の代では成し遂げられないこと」も、ある種、自分の力でやれる。この辺が醍醐味だろうという気がします。もちろん、そのためには「単に自分が個人的にやりたいこと」ではなく、「みんながやりたいこと」「受け継ぐ人がいること」を、考える必要があります。ここが、「組織・個人・未来の交点」ですね。
つまり「人材や組織の活性化」とは、個々人にとっても企業や組織にとっても、“未来への投資” であって、それが上で述べた “結果の可視化”(成功体験)と、“成長期待の可視化” によって連鎖的に起きている状態なのかなと、思っています。
個人としても、組織や企業としても成長する領域に、個人も組織・企業も時間や資源を重点投資し、成果が出続けている状態ですね。理想的ですね。
実はその本質は、これまで何度か取りあげているヴィゴツキーの「ZPD」(発達の最近接領域)と一致するんですよね。
「いまは無理。でも支援があれば、できるかもしれない」
「この仲間となら、そのうちできるようになるはず」
「この人を手伝えば、自分には絶対できないことも、実現できるかもしれない」
これらがかみ合う(≒共鳴する)ことで、人材も組織も活性化していく、どんどん活性化していく、ということだろうなと、今、自分の会社・組織を経営していて思います(笑)。
関係者の皆さん、貴重な機会をありがとうございました。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
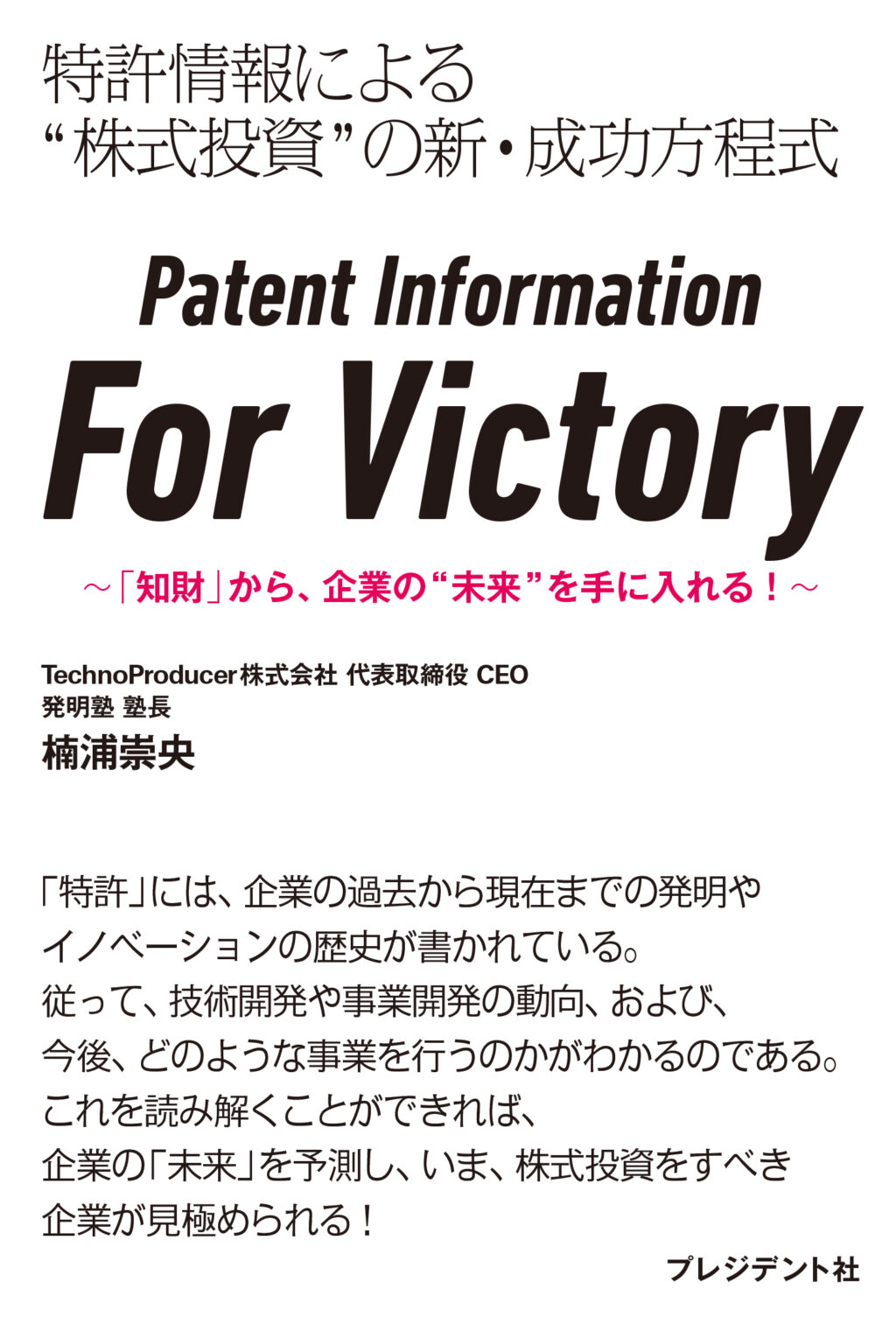
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略