【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、2025年4月に開講し討議を行った「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)」の第3回の振り返りです。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)
これまでの振り返りは以下のコラムをご覧ください。
第1回振り返り:新規事業支援者の心得とは? 成功する提案を導く支援の本質と実践法
第2回振り返り:新規事業「支援者」と「指導者」の違い|たった1回の指導でここまで変わる! 成果を出す支援者育成の本質
企業内発明塾は、第3回で、新規事業の企画書段階に入ります。
ここまでの「情報収集」「最先端へ到達」「突破するアイデアを生み出す」段階とは、やるべきことがガラリと変わります。
ここまでは、よくも悪くも「創造」の段階。
ここからは「証明」の段階。
スクラップ&ビルド、あるいは、ピヴォットを繰り返しながら、「売れる・勝てる・儲かる・できそう・オモロい」を満たす企画へ到達するわけです。
(参考)売れる・勝てる・儲かる
https://www.techno-producer.com/column/how-to-write-innovation-proposal/
それでは、本題です。
支援するには、まず、この段階で提案者の心の中で何が起きるか、を熟知しておく必要があります。
9割の提案者は、こういう状況になります。
一番よくあるのが、「決めたくないので延々と情報を集め続ける」パターンです。
ふわっとした企画、明日から関係者がすぐにテキパキと動き出せない、具体性がない企画で放置される、も結局は同じです。
そういう人はそういうふわっとした企画を量産してしまいます。そして実行しません/されません。
これに陥る人が非常に多い。
しかも本人は、自分が決断から逃げていることに気づいていない。
作業した感/作業している感があるので、進んでいると錯覚し、満足してしまうんですよね。
気づいていないので、独力では修正不可能です。
発明塾では、「コップのふちを舐めて、うろうろして終わる」と表現します。
中に飛び込んで、じっくりと味わうことができないんですよね。
美味しくなかったら、捨てればいいだけなのですが、、、(笑)。
こういう人に「決めましょう!」とせかしても逆効果です。
ここまでの振り返りで、お伝えしている通りですね。
では、どうするか。
相手と状況によって、対応は時に大きく異なりますが、基本原則は以下になります。
① 豊富な選択肢の準備
② “調べ尽くす”より“速く決めさせる”支援
③ “失敗してもいい”と伝え、安心を与える
そもそも前段階で、選択肢が十分あれば、どれかに仮決めできる可能性は高まります。
ただ、一部の方は情報量や選択肢の量に圧倒されて、混乱する可能性がありますので、ケースバイケースなんです。
ちなみに僕は、情報処理能力に自信があるので、選択肢は多ければ多いほど良いタイプです(笑)。
そして、いずれにせよ、早く「もう一歩踏み込む」ように、情報を出していきます。
解像度が上がると、決めやすくなるからです。
決められないから解像度が上がらない、解像度が上がらないから決められない、というジレンマを打破するのは、やはり「的確な解像度」の情報です。
わかりやすく言うと、「今、ビビって決められないでいる人が、決められる程度に、解像度が高い情報を出す」ということです。
最後は、当たり前のようですが、これを徹底できるか。
早く決める、そして、早く失敗することで挽回する時間ができることを理解してもらうのも、重要ですね。
うろうろしてると時間切れになるわけですから。
ただ、早く決めすぎても、スケールの小さな企画になる可能性もあります。
挑戦がないまま企画が最後まで行くと、本人もやる気が起きなくなる。
だから、ケースバイケースなんですよね。
ぎりぎりまで可能性を追求しつつ、パッと決めてもらう。
挑戦してもらうには、タイミングが重要です。
そしてこれは、支援者にしかできません。
本人は、状況の全貌や、そもそも新規事業企画のプロセスの全体像が見えていないことが多いからです。
プロセスを理解して、周りが見えている支援者が、さっと「決めるお膳立て」を行う。
プロとして、気の利いた「裏方」に徹するのが支援者です。
企業内発明塾における中盤、企画段階の支援における、最も重要なテーマが、「決断」です。
支援者は「決断」してもらうために何をするかを考え、行動する。
相手が「決められない」人であった場合、「決断すること」に慣れてもらうことが重要です。
決めたことがないこと、この先どうなるかわからない状況で「決める」「決断する」のは、勇気が必要な面もありますね。
でも、決めないと進まないからその先がわからないわけで、同じところにとどまっていても解決しません。
とにかく決めて、次に進んでもらうしかないわけです。
進んでみれば、進め方は見えてくるし、間違っていれば引き返せばよい。
引き返すなら早いほうが良い。
理屈でわかっていても、それができないのが人間です。
さて、決断に慣れてもらうには、どうすればよいか。
まず「小さな決断」を積み重ねてもらえるように、スモールステップで議論を進めていく。
また、決めやすいように、解像度の高い情報を、小出しにしていく。
小出しにするのは、相手によっては、「情報処理のキャパ」を超えてしまうかもしれないからです。
情報が処理できなくなると、思考停止になり、「決められない」状況に戻ってしまいます。
本末転倒です。
「決めてもらうために、今、どれぐらいの解像度の情報を、どれぐらいの量、どういう順番で、出せばよいか」を、考え抜いて、調べていきます。
ケースバイケースなんですよね。
ちなみに僕は、一気に詳細な情報が欲しいタイプです(笑)。
ただ、相手がどんなタイプであれ、あまりゆっくりもやってられませんので、決められるようになってきたら一気にギアを上げて、加速する。
どんどん決めてもらう。
この「議論のギアチェンジ」も、非常に重要です。
仕事には締め切りがありますからね(笑)。
こんな感じで、「決められない」人を、「決められる」人に育てていく。
決断力を育てていく。
これが、企業内発明塾なんですよね。
スーパーマンはいませんので、周りが、決められるように動いていくことで、「決断」「決める」ということに慣れてもらうしかありません。
自分が何かを決めようと思ったら、何が必要なのか、を自身で経験を通じて理解してもらうしかないのです。
ちなみに僕は、決められないときは、以下の2つのいずれかだと思っています。
① 情報が足りない
② 決める基準が明確でない、あるいは、間違っている
調べすぎる人、つまり、①だと思い込んでる人の大半は、実は②です。
だから僕は、情報を調べる前に②を明確にします。
どんな情報があれば決められるのか、が明確になりますので、必要最小限の調査でサクッと決められます。
これができない人が、多すぎます。
だから、支援者がここを支援すればよいのです。
ここまで読んでいただくと、僕は「こういうタイプ/パターンなら・・・」のように、ある程度パターン化して対応していることがわかるでしょう。
完全な正解はありませんが、ある程度、タイプごとに有効な支援の進め方があります。
タイプは「個性」と言い換えてもよいでしょう。
「ビビり」の人は、言い換えれば慎重派だということです。
あるいは、現実派の場合もあります。
いずれにせよ僕は常に、この「支援パターンx個性」を意識して支援しています。
ただ、その「個性」が、決めつけになってはだめだと思っています。
これは「動機づけ面接」の話です。
(参考)「変わりたい」を導く動機づけ面接
https://www.techno-producer.com/jukucho-room/motivational-interviewing_1/
慎重に見える人であろうが、大胆に見える人であろうが、そのスタンスは、常に揺れ動いています。
挑戦したいけど、挑戦したくない。
決めたいけど、決めたくない。
この 心の動きを「読む」ことが、最も重要です。
その上で、決められそうなタイミングで一気に情報を畳みかけて、さっと決めてもらう。
「挑戦」「飛躍」への後押しをするわけですが、単に「後ろからぐっと押す」という感じではありません。
それだと「突き落とす」感じになってしまいます(笑)。
そうではなくて、「ブランコ」のイメージで、「揺らぎを増幅」させていく。
ある程度増幅されると、勝手に飛び出していく。
自然に「決断すること」を決断する。
こんな感じですね。
現在、ある企業様の月額顧問サービスで「動機づけ面接」のレクチャーを行っているのですが、その受講者のコメントが非常に参考になります。
発明塾の支援の肝が、「動機づけ面接理論」であることを、受講者の方のコメントで改めて確認できています。
詳細は次回紹介しますが、「決断」に関するコメントを抜粋紹介しておきます。
楠浦さんの企業内発明塾は ”決断”という事をよくよく考えます。企画の中に決断が無い、企画はたぶんですが判断してもらう以前の”お話し”で終わってしまう。
自分が決断してないと、上の人も決断してくれませんからね。
これは、経営者から見たら当たり前なのですが、現場から見たら当たり前ではない。
経営者は当たり前だと思っているのでいちいち言わないが、現場は、言われてないので理解していない。
そんな感じです。
僕は社員にいつも、こう伝えています。
「決めたけど確認してほしい(承認してほしい):決裁」のか、「決められないから決めてほしい:決断」のか、それ以前の「アイデアが欲しい・情報が欲しい:相談・雑談」なのか、この3つしかないはずなので、どれなのか「決めて」から相談して
「決める人」「決断する人」を育てていくのが、支援者。
決めてもらうために、自分は何をすべきなのか。
前職のスタートアップで、創業直後で状況が非常に流動的な時期に、社長に1年間ついて回ったのが大きかったかもしれませんね。
日々、社長にいろいろなことを決めてもらう必要があるのですが、そのために何を伝えるべきか、肌感覚で理解できました。
僕は、決めたことがないことを決めるためには「頭がちぎれるぐらい考える」必要があると思っているのですが、それをどこまで支援できるか。
自分も「頭がちぎれるぐらい」考えられるか。
考えてみてください(笑)。
よろしくお願いします。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
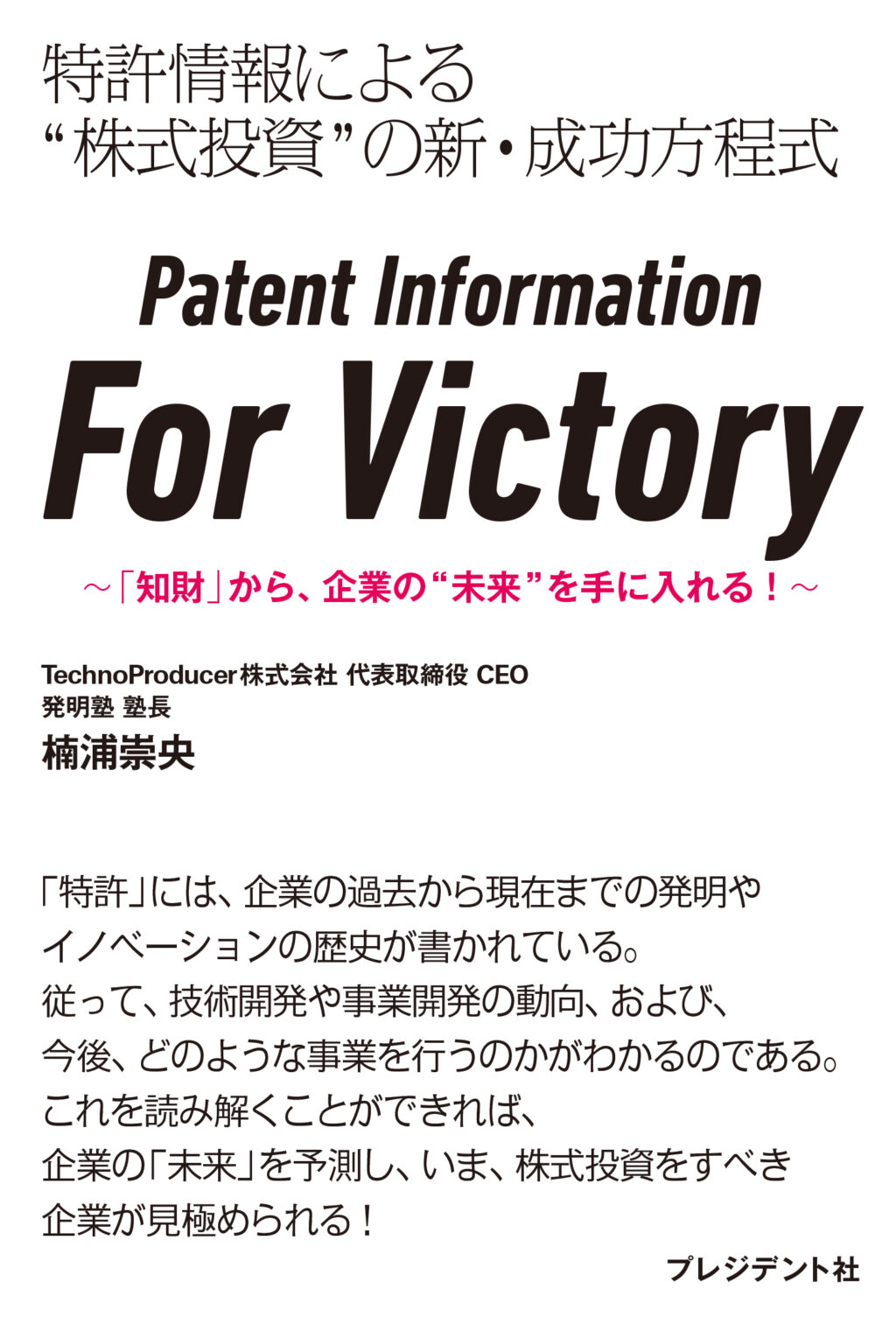
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略