【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は「発明塾が理想とする新規事業の支援」について、認定新規事業サポーターの方と「月額顧問サービス」の中で行った壁打ちのまとめ(お声)紹介、その2です。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)
前回コラムは以下をご覧ください。
新規事業支援者として「両価性」と「動機づけ面接」で挑戦を支える(1)両価性を理解する──「変わりたいけど変われない」心理をどう支援するか
「支援者」に必要なスキルとして、僕が重視する「動機づけ面接」のお話です。
さっそく本題へ。
==ご本人の振り返りメモ(お声)より
※ ご厚意により、全文そのままの掲載を許可いただきました
【4. 行動変容を促す仕組みの限界】
企業ではしばしば、報酬や罰といったインセンティブ、動機付けによって行動を促そうとする。
たとえば:
「2ヶ月以内に結果が出なければ評価が下がる」
「成果を出せば賞与・昇進の対象になる」こうした“アメとムチ”のアプローチは、短期的な結果には有効であっても、この手法はアメが青天井になる可能性があり、いずれ見合わない報酬に対して動機が薄れていく可能性がある。
【5. コンフォートゾーンと変化のリアリティ】
企業内の新規事業担当者は、たとえ成果が出なくても(考課に影響はあれど)給与は支払われる。これにより:
・失敗しても経済的リスクは低い(給料は払ってもらえる)
・無理に動かなくても責められないという「安心できる停滞」が成立してしまう。
一方で、ベンチャー経営者は成果を出さねばキャッシュが尽きる。これは行動を強制する環境であり、確かに動機付けとして強力ではある。
ただしこの場合も、「生存プレッシャーによる行動」であり、他律的動機付けの一形態であることに変わりはない。【6. 両価性をどう扱うか】
「動機付け」とは、こうした両価性を乗り越えるプロセスに他ならない。
大切なのは:
「やりたい」と「やりたくない」が同時にあるのは自然なこととして受け入れる
100%の確信を持つ必要はない。“ゆらぎ”があるのが人間らしさ
「やりたい」「やりたくない」はいずれも主観である。
それを無理に突き詰めて「内側からあふれ出るものを見つけよう」とする行為は、時として主観を主観で追い詰める自己内拷問になりかねない。
さらにそこに他者の主観が干渉すると、もはやそれは仕事ではなく「互いの主観のぶつかり合い」という曖昧で不安定なものになる可能性がある。(次回へつづく)
==メモ、ここまで
今回も、メモをベースに、私が普段「動機づけ面接」の考えを用いて「新規事業の支援」をどのように行っているか、お話しします。
【4. 行動変容を促す仕組みの限界】
企業ではしばしば、報酬や罰といったインセンティブ、動機付けによって行動を促そうとする。
たとえば:
「2ヶ月以内に結果が出なければ評価が下がる」
「成果を出せば賞与・昇進の対象になる」こうした“アメとムチ”のアプローチは、短期的な結果には有効であっても、この手法はアメが青天井になる可能性があり、いずれ見合わない報酬に対して動機が薄れていく可能性がある。
新規事業に限らず、
「XXしたらいいことあるよ」「XXしないと罰せられますよ」
みたいなものが「行動を促す」ために用いられること、結構多いですよね。
たしかに、これが効果的なケースも、たくさんあります。
でも新規事業の場合、これってどれぐらい意味(効果)があるんだろうか?そしてデメリットはないんだろうか?と、僕はいつも思っています。
新規事業にチャレンジする意欲は評価したいところですが、実際問題としてまったく儲かっていない新規事業のために、多額のボーナスを出すのも、なんかおかしいかもしれませんよね。既存事業の利益を削って支払うわけなので、既存事業の方からそれなりの反発が出そうです。
とはいえ、既存事業と同じ尺度で、「儲かった分だけボーナスが出ます」としてしまうと、誰もやりたがらないでしょう(笑)。
チャレンジに対する褒賞は、何らかの形で出したいところなので、なかなか難しいですね。
一部の企業では、提案に対する報奨金や、マイルストーン達成ごとのインセンティブが設定されているようです。
ちなみに、僕がコマツで新規事業に関わっていたときは、そんなしゃれた制度はありませんでした。時代ですね。
やりたいようにやらせてもらっていたのと、経営の勉強ができたので、個人的には苦労に見合って余りあるゲインがあったかなと思ってます。
あと、会社のお金はもちろんですが、すでにあるインフラや人脈が使える、というのは結構大きかったですね。
これは、その後スタートアップを立ち上げて資金調達してみてわかりました。
誰もいないし、何もないので、どれだけお金を集めても全く足りない(笑)。
5億円10億円が、設備投資と人件費で、あっという間に消えていく世界でした。
肩書はCTOなのですが、お金を数えるのが仕事でしたね(笑)。
【5. コンフォートゾーンと変化のリアリティ】
企業内の新規事業担当者は、たとえ成果が出なくても(考課に影響はあれど)給与は支払われる。これにより:
・失敗しても経済的リスクは低い(給料は払ってもらえる)
・無理に動かなくても責められないという「安心できる停滞」が成立してしまう。
一方で、ベンチャー経営者は成果を出さねばキャッシュが尽きる。これは行動を強制する環境であり、確かに動機付けとして強力ではある。
ただしこの場合も、「生存プレッシャーによる行動」であり、他律的動機付けの一形態であることに変わりはない。
これは、非常にわかりやすいですね。
既存事業が存在する企業における新規事業は、多くの場合、成果が出なくても、短期的に大勢に影響はないでしょう。
だから、失敗しても責められません。このこと自体は、良い面もあるでしょうね。
ただ、この方が指摘している「安心できる停滞」にはまる可能性は、極めて高いですね。
実際、僕が新規事業を担当していた時も、「楠浦くんは、何を生き急いでいるのか?」と、しょっちゅう言われました(笑)。
僕はもともと、典型的な関西人で非常に短気なので、早く結果を出したいタイプなんですよね。こういう人は、意外に新規事業に向いている気がしています。
誰にも何も言われなくても、とにかく早く結果が出したいという「性格」ですからね(笑)。
一方、ベンチャー・スタートアップは「売り上げがないと死ぬ」存在です。だから、すぐに売り上げが立つように、常に動きます。
でも、これも結局、「お金」というインセンティブというか、資金ショートの「恐怖」に動かされてるだけだよね、というのが、この方のコメントです。
はい、おっしゃる通りです。
DeepTechで、ほんとにゼロからのスタートアップになると、5憶10億では足りませんからね。
分野にもよりますが、例えばナノテク分野だと、計測装置をいくつか買ったら数億円が飛んでいきます。
今の弊社でも、僕は常に「お金」の心配ばかりしています(笑)。
まぁ、短気なので、この仕事は僕には向いている気がします。
明日売れないと死ぬ、という生活を20年以上、好き好んで毎日やっているわけです。
極めつけの変人でしょうね(笑)。
だから僕は、企業内発明塾でも「すぐに売れるところを探す」作業を、無意識のうちに始めます。
もう、これはある種の病気ですね(笑)。
でも、僕にとっては便利な病気です。
毎日やってると、膨大なノウハウと情報が、どんどん蓄積されるからです。
【6. 両価性をどう扱うか】
「動機付け」とは、こうした両価性を乗り越えるプロセスに他ならない。
大切なのは:
「やりたい」と「やりたくない」が同時にあるのは自然なこととして受け入れる
100%の確信を持つ必要はない。“ゆらぎ”があるのが人間らしさ
「やりたい」「やりたくない」はいずれも主観である。
それを無理に突き詰めて「内側からあふれ出るものを見つけよう」とする行為は、時として主観を主観で追い詰める自己内拷問になりかねない。
さらにそこに他者の主観が干渉すると、もはやそれは仕事ではなく「互いの主観のぶつかり合い」という曖昧で不安定なものになる可能性がある。
前回コラムでお伝えした通りなのですが、僕が知る限り、どの企業にも「新しいこと」にチャレンジできる能力と意欲のある方が、十分な数、存在します。では、そういう方が、「私、新規事業やりたいです!」と手をあげてくださるかというと、そんなに簡単ではない。
そこは「お金」などのインセンティブの話にするではなく、
「変わりたいけど、変わりたくない」
つまり、
「新規事業、やってみたい、なんか面白そう、挑戦してみたい、成長したい」
「でも、失敗するのは怖い、めんどくさい、今は忙しい」
という両価性に向き合うことを、まず優先してほしいなと思っています。
その上で、挑戦して、自ら苦労を買って出てくれた方にどう報いていくか、考える。
まずは「やりたい」と動き出してもらう、あるいは、「これならやりたい」というものを見つけて、動き出してもらう。
ココにフォーカスしたいなと、僕は考えています。
これが、僕の、そして、発明塾の考え方であり、支援法なんですよね。
ただし、この方が指摘しているように、「何かやりたいこと考えろ!」という「押し付け」は、やっぱり駄目だと思ってます。
昔、ある企業の方に「とにかくやりたいことが見つかるまで、問い詰める」みたいな新規事業や研究テーマ創出の場を、社内に設けている、という話を聞いたことがあります。
その企業さんではうまく行くのかもしれませんが、僕はちょっと「怖いな」と思ってしまいました(笑)。
自発性を押し付けるって、なんか変だなと。
「主観を主観で追い詰める自己内拷問」
「互いの主観のぶつかり合い」
みたいなことに、ならないかなと。
発明塾は、そういうことはしません。
発明塾の考える「支援」とは、両価性と向き合いながら、小さな挑戦の芽(アイデア)と挑戦の気持ちを「育てていく」ことなんですよね。
この
「挑戦の芽」(アイデア、思いつき、興味、オモロいと思う気持ち)
「挑戦の気持ち」(両価性の中で揺れ動くもの)
の両方に注目するのが、大事なんです。
ただ単に、「売れそうだと思うアイデア」を押し付けて盛り上がる、ということではないんですよね。
両価性の中で揺れ動き気持ちに寄り添い、その様子を見ながら、少しずつ育てていく。
これが、発明塾の支援なんですね。
だから「動機づけ面接」の技術が欠かせないんです。
公開講座でも、このあたりの考え方を良く解説し、実践してもらいました。
「動機づけ面接」の手法を用いた「新規事業の支援」「IPランドスケープ」にご関心がある方は、ぜひお問い合わせください。
動機づけ面接を基礎から学びたい方は、その旨お伝えください。ゼロから指導いたします。
月額顧問サービス
https://www.techno-producer.com/advisory-service/
こちらからお問い合わせください。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
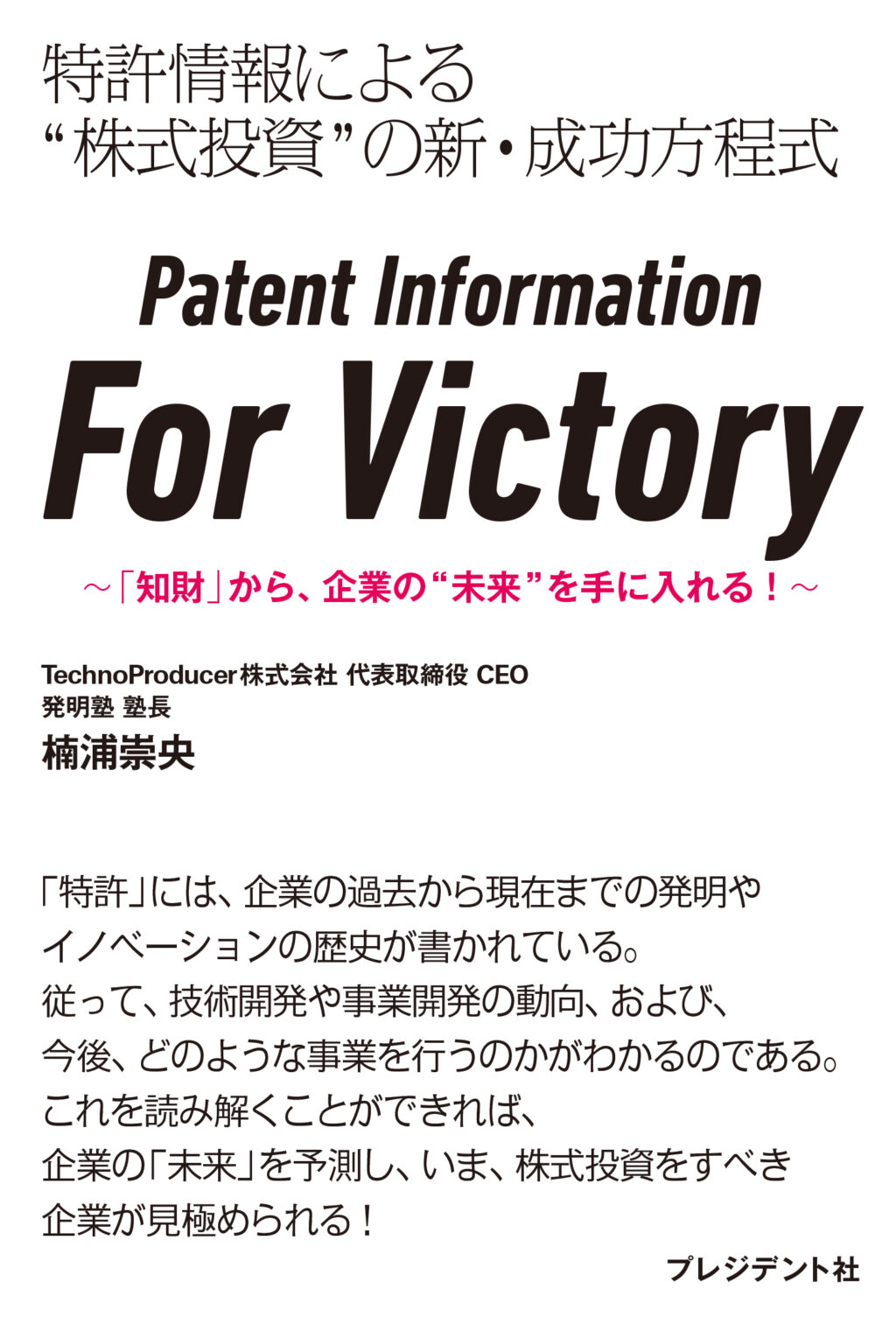
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略