【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、2025年4月に開講し討議を行った「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)」の第4回の振り返りです。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)
これまでの振り返りは以下のコラムをご覧ください。
第1回振り返り:新規事業支援者の心得とは? 成功する提案を導く支援の本質と実践法
第2回振り返り:新規事業「支援者」と「指導者」の違い|たった1回の指導でここまで変わる! 成果を出す支援者育成の本質
第3回振り返り:決断力を育てる新規事業支援|「頭がちぎれるほど考えたか?」で成果を変える
企業内発明塾は、第3回と第4回が、自身の新規事業の企画について「確信犯」になっていただく時間です。
第5回以降は、それを「確実に伝える」ためのワークを行います。
つまり、第4回で「詰め切る」必要があるわけですね。
ここで確信できない内容は、「伝える以前」の問題になります。
自分が信じていないものを提案して、相手に伝わる理由がありませんよね。
ここでは、「新規事業の企画段階」における支援者の役割と、気をつけるべきポイントについて、実際の討議内容を元に紹介します。
第4回は、「確信犯」になれる提案者と、確信犯になれずに「ウロウロを繰り返す」提案者で、大きく差がついてしまうタイミングでもあります。
正確には、「差がついていることが目に見えてわかる」タイミングだ、と言えるでしょう。
そこで、支援者は何ができるのか。
支援者として成長すべく参加された方の、今回のワークショップ/ワークショップ前の準備作業に関するコメントを一つ挙げておきます。
支援者・参加者共通で、皆さんができていない内容の「ダントツ・ナンバーワン」だと思います。
具体的に「何をします」「何(課題)を解決します」「あなたの代わりに何をします」と顧客に約束するのか?
→これは「決め」の問題。自分はこの決めるという作業が苦手だと気が付いた。すごく決めるのが怖いなと感じました。(日和ってる感じ。当たってるかどうかわからないので。でも決めるしかない。決めて、さきに進んでみて、間違っているなら戻ればよい。)決めの問題はこれまでの調査から得られた情報わかっていることを参照して、不安だけど、具体的に、明確に決めるしかない。そして、支援者は提案者が決めやすくなるように情報やコメントを出す動きをする
では、本題へ。
この記事の内容
提案者が作業をしても、進まない。ワークショップで討議をしても、進まない。
何が原因でしょうか。
提案者はもちろんですが、支援者による、「今すべきこと」についての“見立て”が不十分であることも少なくありません。
たとえば、第4回になって、支援者自身が単に「調べる」を続けてしまうことで、結論が先送りになる、次に進めない。
散らかってしまうわけですね。
第3回、第4回で重要なのは、「絞り込み」「確信を持つ」ための調査です。
ここで重要なことは、今、何を決めるのか、を明確にして調べること。
今ここで何を決めるべきなのかを、全員が理解して調べることです。
今回も実際、「決めるのが怖い」「ヒヨってしまう」という声が、支援者から出ていました。
あなたがビビッてどうするんだ、という話ですね(笑)。
提案者が余計ビビってヒヨるだけです。
足を引っ張ってしまいます。
後述する「エコノミック・モート」(経済的な堀)等の知識や、該当する他業種の事例などを駆使して、素早く決めるための調査を行うのが、支援者の役割です。
企業内発明塾には「エコノミック・モート」に関するテキストもあります。
まず決めることは、「最初の一歩をどう踏み出すか」ですね。
壮大な企画を立てても、「結局、明日から何するの?」がないと進みません。
今回は「ファーストユーザー候補に営業に行くなら、どんなチラシが必要か?」という問いを僕のほうから出して、作業することにしました。
これにより、
が、具体化します。
顧客価値仮説を、一気に具体化する作業ですね。
実際、企画が通ったらチラシをつくってヒアリングに行くわけですから、それを前倒しで行って、「明日営業に行くなら何を決めないといけないか」を明確にするわけです。
新規事業は「売り」(セールス)から入る。
これが、発明塾の鉄則です。
作ったけど売れませんでした、開発したけど商品化されませんでした、は最悪ですからね。
ただ、「過剰に売り込む」ような売り文句は、必要ありません。
営業に不慣れな方は、魅力的なセールストークを考えようとして、「盛りすぎる」傾向にありますが、それは不要です。
端的に、顧客の課題を指摘して、解決できることを伝えるだけでよいのです。
それで売れるのがファーストユーザーです。
売り込まないと売れないなら、ファーストユーザーか、顧客価値仮説のいずれかが間違っています。
そこまでしなくても勝手に売れていく。
これがファーストユーザーです。
実際には、営業経験を通じて肌感覚で理解していくものなので、なかなか理解されない場合は、僕の経験談などを話しながら、進めていく場合もあります。
第4回は、「決める」の最後のタイミングです。ここで決めないと、時間切れです。
では、このタイミングでの、
「支援者の本質的な仕事とは何か?」
考えてみましょう。
それは、限られた時間の中で提案者が前に進めるよう、“段取り”を整えることですね。
支援者が勝手に決めるわけにもいきませんので、
これらを明確にしたうえで、提案者のキャパに応じた“絞り込み”を行うことが、支援者に求められる技術です。
この、「キャパに応じた」の部分が、非常に重要です。
準備作業が不十分だったり、決め切れない提案者の多くは、そこまでに出た情報に対して情報処理のキャパが不足している場合が多いんですよね。
消化不良で決め切れない、進まない。
ここでさらに情報を投下しても悪循環ですから、「わかっていることで、決められることを決めていく」作業の支援が求められます。
情報を増やすのではなく、絞り込む。
「決める」とは、そういうことですよね。
提案者の成長なくして、よい新規事業企画の提案と、企画の実現はありません。
支援者が情報を揃えても、提案者が「理解して」「判断して」「動ける」状態でなければ、何も始まらないからです。
かといって、残り2回というタイミングで悠長には進められないので、以下を念頭にピッチを上げて進めて行くことになります。
発明塾では、ワークショップでは「集まったときにしかできないこと」をやりましょう、としています。
今回は、日常のSNSでのやり取りでは難しい「決める」経験を、リアルタイムでトレーニングを兼ねて行いました。
「今から何をするのが良いのか」「どこに絞り込んで検討を進めるのが良いのか」を素早く議論しつつ、全員の良いところを取り入れた方針を決めていく手法が、発明塾にはあるんですよね。
参入障壁(Economic Moat)とは、企業が競合他社の参入を阻み、競争優位性を維持するための要素のことです。
事業の中で、これをどう形成していくか。
これが、企画段階での議論の肝の一つです。
第3回、第4回の企画の段階になっても、引き続き技術の話に終始する人もいますが、技術的にできそうであることは、第1回、第2回である程度確認が済んでいるはずです。
だから、企画段階では「ファーストユーザーと顧客価値」「売れる・勝てる・儲かる」など、事業の言葉で話す必要があります。
いつまでも技術の言葉で話す人は、要注意です。
今回のワークショップでは、「業界構造」「規制」「物流を含む販路の仕組み」などについても、話をしました。
これにより、参入障壁が形成されるのか、形成できるのか。
それらはどの程度強固なものになりそうか。
異業種の事例なども参考に、考察していきました。
企画が農業に関するものなので、
など、業界の力学にもとづいた考察を行っています。
実際の事業において、どこが参入障壁になるのか、見極めつつ強化していくわけですね。
エコノミック・モートについては、日ごろから様々な企業の事例を分析しておくことが重要です。
支援者として的確な活動ができるかどうかに、直結します。
僕が「投資」の話をすると、すぐに「どこに投資したら儲かるんですか」みたいな話をする人がいますが、僕はそこにはあまり興味がないんです(笑)。
そういう人に限って、「儲かる」の定義もあいまいで、金額の話なのか割合の話なのか不明ですし、いつまでに、も不明。
そもそも「シャープレシオ」のようなリスクとの対比で考えてない人も多いですし、とにかく話がめんどくさいんですよ(笑)。
過剰なリスクをとったら、過剰なリターンがあって当然ですからね。
リスクに比して儲かってない限り、僕は儲かったとは思わないんです。
僕は、儲かり続けている企業と、そうでない企業の違いは何なのかを知りたいという、純粋に経営者としての必要性と興味にしたがって、企業を毎日分析しているだけなんですよね。
決算や、世界中の投資家の分析を見ると、非常に勉強になる。
ほんとはただそれだけなんですが、僕が詳しくなると、皆さんがさらにいろんなことを教えてくださるので、なんとなく楽しいのは事実ですね(笑)。
楽しくなければ、毎晩何時間も企業の決算ばっかり読めない(笑)。
特許も見るので知財戦略もわかりますし、知財で勝ってる企業、知財で勝ってるけど事業で負けた企業、いろんな事例が毎日見つかって非常に面白いです(笑)。
最近も一つ、オープン・クローズ戦略を仕掛け間違って、(少なくとも今は)負けている企業の事例がありました。
勝負の世界は競合がありますから、「XX戦略なら勝てる」とかは無いんですよね。相手に読まれて、上手を取られたら負けます。
そういう事例が、ありました。
勉強になります。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
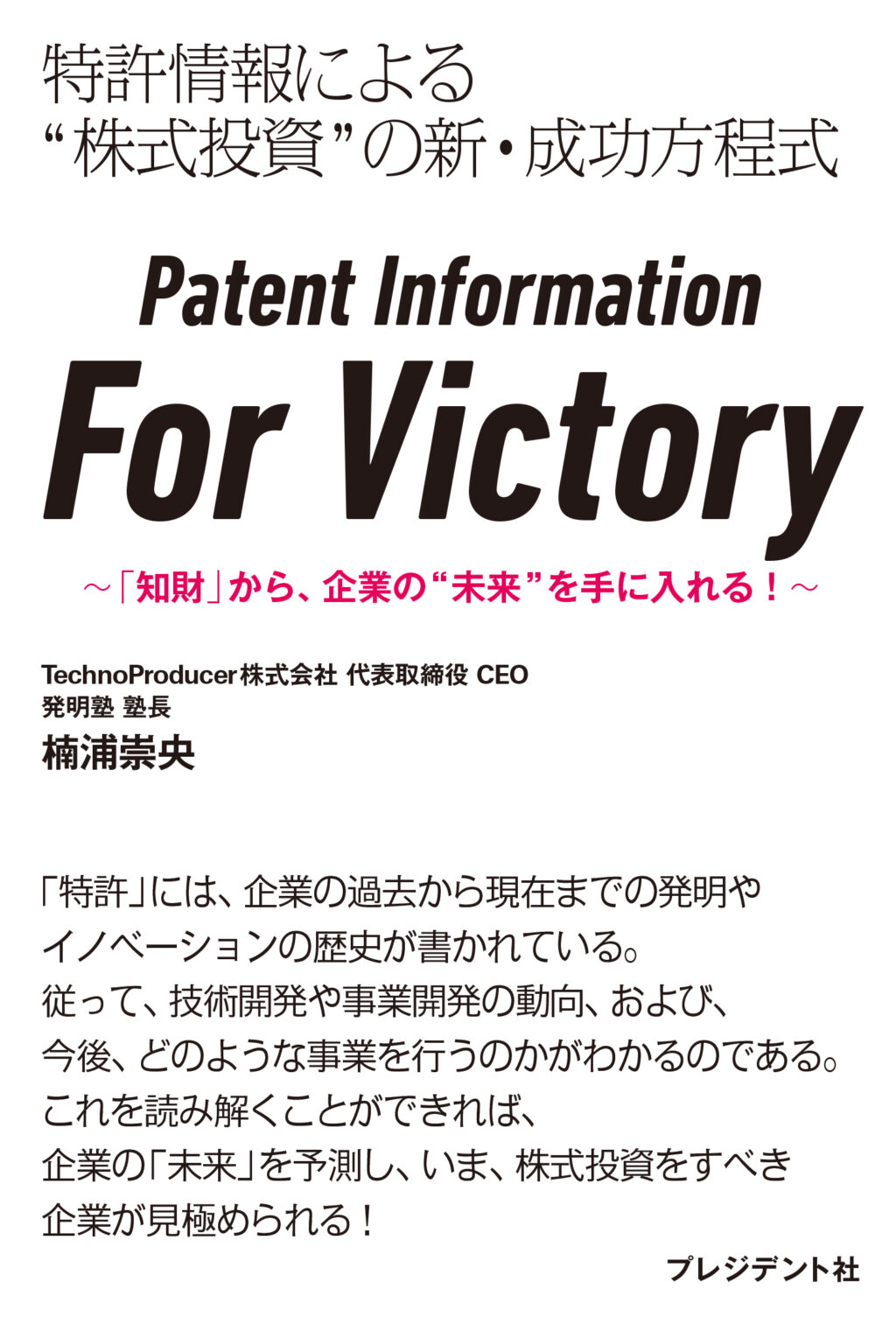
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略