「発明塾」塾長の楠浦です。
企業内発明塾参加者のお声とともに、「発明塾で何をどう教えているか」を紹介しています。
今回は、企業内発明塾に支援者として参加されている方の「第3回討議」後のお声を紹介します。
討議は全6回ですので、中間地点ですね。
第3回は、まだまだ悩みが多いタイミングですが、この辺で「一気に道が開ける」「霧が晴れる」方が多い印象です。
僕がいつもお話しするのは、「水の入ったコップに、石を入れていく」というたとえ話です。
コツコツ石を入れているけど、なかなか水はあふれ出ない。
でも、そこであきらめると終わり。
あるタイミングで、一気に出てくる。
知的な作業って、多くは、こういう感じだと思います。
イメージの世界ですね。
でも、イメージを持てないものは、人間は実現できないんですよね。
漫画・アニメ「葬送のフリーレン」でも、主人公の魔法使いが「魔法はイメージの世界だ」と言っています。(何の話?笑)
話を元に戻しましょう。
・新規事業提案が進まない、提案が集まらない
・新規事業について、「ノーアイデア」の状態で進まない、進め方が分からない
・漠然としたアイデアはあるが、考えても同じところをグルグルするだけでまったく深まらず、堂々巡りで時間だけが過ぎていく、提案につながらない
・考えるアイデアは、すでに他社が手掛けているものばかりだ、どうすればよいか途方に暮れている
・新規事業や研究テーマを積極的に提案できる人材を育成したい
という方々に、ぜひご転送や回覧含め、ご紹介をお願いします。
「企業内発明塾参加者の方」による、「人を動かす企画じゃないとスタートは切れない」「モノだけ勝手に作って売ってこい、じゃ営業は動かない」「顧客リストは開発者が作るもの」「人が、これなら動きます、という企画を作るのが開発の仕事」というお声を取りあげ、発明塾の指導内容や考え方を紹介します。
受講者の興奮度と熱気をそのままお伝えするため、あえて当方で校正を入れず、原文のまま紹介します。
原文の勢いって、大事なんですよね。
==お声、ここから
組織を、人を動かす企画でなければスタートは切れない。
なんで今までの 新規事業、商品がうまく行かないか?の理由の一つが見えた。今回 顧客リストをつくるのは開発者、技術者の仕事と言い切った楠浦さんの言葉に衝撃をうけました。なぜならば私は逆の考えでした。私は営業が考えること、事業部が考える事とどこかそのような考えでした。実は昨日 衝撃をうけてしばらく頭が真っ白だったのです。
振り返ってみて出てきたのは 「うまくいかない理由の一つとして言えるかも。モノだけ勝手につくって 誰かに売ってこいじゃ」 関係者が動くわけないですね。仮に社長が売ってこい!と命令すれば動くかもしれませんが、それって動きたいということではないんですね。皆がそんなテンションではうまくいくわきゃないわなと。
組織が、人が これなら動けますという企画をつくるのが 「開発」という仕事をする者の 最低限求められる力量なのかも?と考えます。
いずれにしても 直接、しかも1on1で やらせてもらっているからこそ 直に脳に届いた話でした。
残り 4~6で 作り上げることは 組織、人を動かせる企画書(にしたい。)です。部品メーカー(東証プライム市場上場)企画部門の方
==お声、ここまで
熱い(笑)。熱いっすね(笑)。
いや、僕じゃなくて、この方が(笑)。
今回も、一つひとつ見ていきましょう。
組織を、人を動かす企画でなければスタートは切れない。
なんで今までの 新規事業、商品がうまく行かないか?の理由の一つが見えた。
ビジネスやコミュニケーションに関する分野で有名なアメリカの作家 デール・カーネギー の名著の一つに「人を動かす」という本があります。
もちろん僕も持ってます。
「人を動かす」という言葉というか言い回し自体は、僕はあまり好きではないのですが、この本に書かれていることは、ホントその通りだなということばかりです。
「自分一人では何もできない」という、ある種のあきらめというか、「覚悟」を持つことが、組織では重要になります。
もちろん、「最後は自分一人になっても頑張るぞ」という覚悟も必要なんですけどね。
こういう、「矛盾した精神状態」を適切に操って、成果を出すのがリーダーの仕事だ、と僕は考えています。
アメリカの小説家 スコット・フィッツジェラルド も、同じようなことを言っていますね(笑)。
今回 顧客リストをつくるのは開発者、技術者の仕事と言い切った楠浦さんの言葉に衝撃をうけました。なぜならば私は逆の考えでした。私は営業が考えること、事業部が考える事とどこかそのような考えでした。実は昨日 衝撃をうけてしばらく頭が真っ白だったのです。
振り返ってみて出てきたのは 「うまくいかない理由の一つとして言えるかも。モノだけ勝手につくって 誰かに売ってこいじゃ」 関係者が動くわけないですね。仮に社長が売ってこい!と命令すれば動くかもしれませんが、それって動きたいということではないんですね。皆がそんなテンションではうまくいくわきゃないわなと。
実はこれ、僕が前職と現職で、たびたび経験したことなんですよね。
前置きとして、新製品開発、ある程度ベースがある新規事業開発、完全にゼロイチの新規事業開発、の違いを、説明します。
川崎重工時代は、オートバイの新機種開発担当で、エンジン設計を一人ですべて担当していました。
結構大変な仕事ですが、開発して出せば必ずある程度売れます。販売店があるからです。カワサキファンもいます。
これは新製品開発ですね。
コマツ時代の新規事業では、ある程度の規模の顧客を先に見つけてから、開発に着手しています。
その上で、技術開発しながら、さらに顧客開拓をしていくというサイクルを、回し始めたところでした。
これは、ある程度ベースがある、新規事業開発ですね。
(最初の顧客を見つけるところは、ゼロイチの部分が少しありますが、見つけさえすれば売るものはあったので、やはり土台があったと言えるでしょう)
前職のナノテクスタートアップは、設立当初「技術はない」「顧客も想定していない」という、完全に「ゼロイチ」の取り組みです。
ある程度の市場ターゲット(これが曲者です 笑)と、世に受け入れられるために到達すべき、最低限の技術レベルはわかっていましたが、具体論はなかったんですね。
そんな状態であるにもかかわらず、「ナノインプリント装置を売りましょう」「代理店にお願いしましょう」で、売れるわけがない(笑)。
代理店の営業担当者も、誰になんて言って売ったらいいかわかりませんので、最初は「こんな面白そうなものがありまして」と、アポ取りの話題の一つとして紹介してくれましたが、そのうち忘れ去ってしまいます(笑)。
自分でやってみるとわかりますが、営業現場では「売れるモノを売る」ことに徹するのが普通なので、「これを売ってください」と言っても、営業担当者は売らないんですよね。売れたらなんでもいいので(笑)。
なので僕は、「最初は自分で売ってみたらいいですよ」と、すべての起業家と技術者にお伝えしています。
「何がどうなると売れるのか」「誰がどう売っているのか」を知らないで、「これで売れます」「売ってください」とか言っても、説得力のかけらもないんですよね(笑)。
さて、最初は自分で売ってみる前提だと、「顧客リスト」作りが最も重要になります。
逆に、「顧客リスト」があれば、周りの人も「その会社知ってるよ」「その人知ってるから紹介する」「その人は知らないけど、同じ部署の人を知ってる」となって、つながっていくんですね。
だから、自分で売らなくて済む(笑)。
非常に不思議なことに、「自分で売るつもりで顧客リストを整備したら、誰かが売り始める」という状況が、勝手に生じます(笑)。これが「企画」の威力です(笑)。
企画とは、こういうことを指すんですよね、僕の中では。
命令しても動かないけど、自分が覚悟を決めると、周りが勝手に動く。
それが「企画」「企画書」「企画提案書」の目指すところです。
もちろん、自分で動いてもオッケーです(笑)。
組織が、人が これなら動けますという企画をつくるのが 「開発」という仕事をする者の 最低限求められる力量なのかも?と考えます。
いずれにしても 直接、しかも1on1で やらせてもらっているからこそ 直に脳に届いた話でした。
残り 4~6で 作り上げることは 組織、人を動かせる企画書(にしたい。)です。
僕が設計者(Architect, Designer)だからということもありますが、発明塾では「企画書は設計図」「発明提案書は設計書」だと、いつもお話していますね。
設計図は、設計者個人の手を離れて、それだけで人を動かす力を持ちます。
設計図を、現場で作業者に説明している人をたまに見かけますが、それが必要なのであれば、設計者失格です。
設計図が不完全だ、あるいは、相手に伝わらないものになっている、ということだからです。
僕は、カワサキとコマツ時代に、「現場から電話がかかってきたら負け」というルールを、自分に課していました。
もちろん、毎日電話がかかってくるので(苦笑)、100戦99敗ぐらいなのですが、そこで分かったことは、「何が相手がわからないか」「何が書いてないと相手が動かないか」、考え抜いてすべて図面に書け、ということです。
現場の作業者の方によっても「わからない部分」は変わるので、終わりのない作業なのですが、ある程度の法則性というか「肝」があります。
ここを押さえれば、大きなトラブルは起きない、という部分ですね。
肝の部分を押さえて「人を動かす」設計図、「人と組織が動く」企画書を作らないと、どんなに良いアイデアも企画も、価値はゼロです。
誰も動かないなら、すべてが無駄になります。
企画する以上、絶対に動いてもらう。そういう企画提案書を作るのが、発明塾です。
(もちろん、誰も動かないなら自分で動いて、絶対に無駄にはしないのですが)
こういうことを僕が皆さんと一緒にやっていく上で、「いずれにしても 直接、しかも1on1で やらせてもらっているからこそ 直に脳に届いた」っていうのも、大事なんでしょうね。
「ワン・オブ・ゼム」(One of them)だったり、自分の企画でない、なんかヒトゴト、他人事、だと「脳に直で届く」ことはないんでしょうね。
僕だけが頑張っても、何も起きないわけです。
皆さんも、是非、「脳に直で届く」のが特徴の「発明塾」をご活用ください(笑)。
企業内発明塾でも、月額顧問でも、「1on1」は可能です。
・新規事業提案が進まない、提案が集まらない
・新規事業について、「ノーアイデア」の状態で進まない、進め方が分からない
・漠然としたアイデアはあるが、考えても同じところをグルグルするだけでまったく深まらず、堂々巡りで時間だけが過ぎていく、提案につながらない
・考えるアイデアは、すでに他社が手掛けているものばかりだ、どうすればよいか途方に暮れている
・新規事業や研究テーマを積極的に提案できる人材を育成したい
という方々に、ぜひご転送や回覧含め、ご紹介をお願いします。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
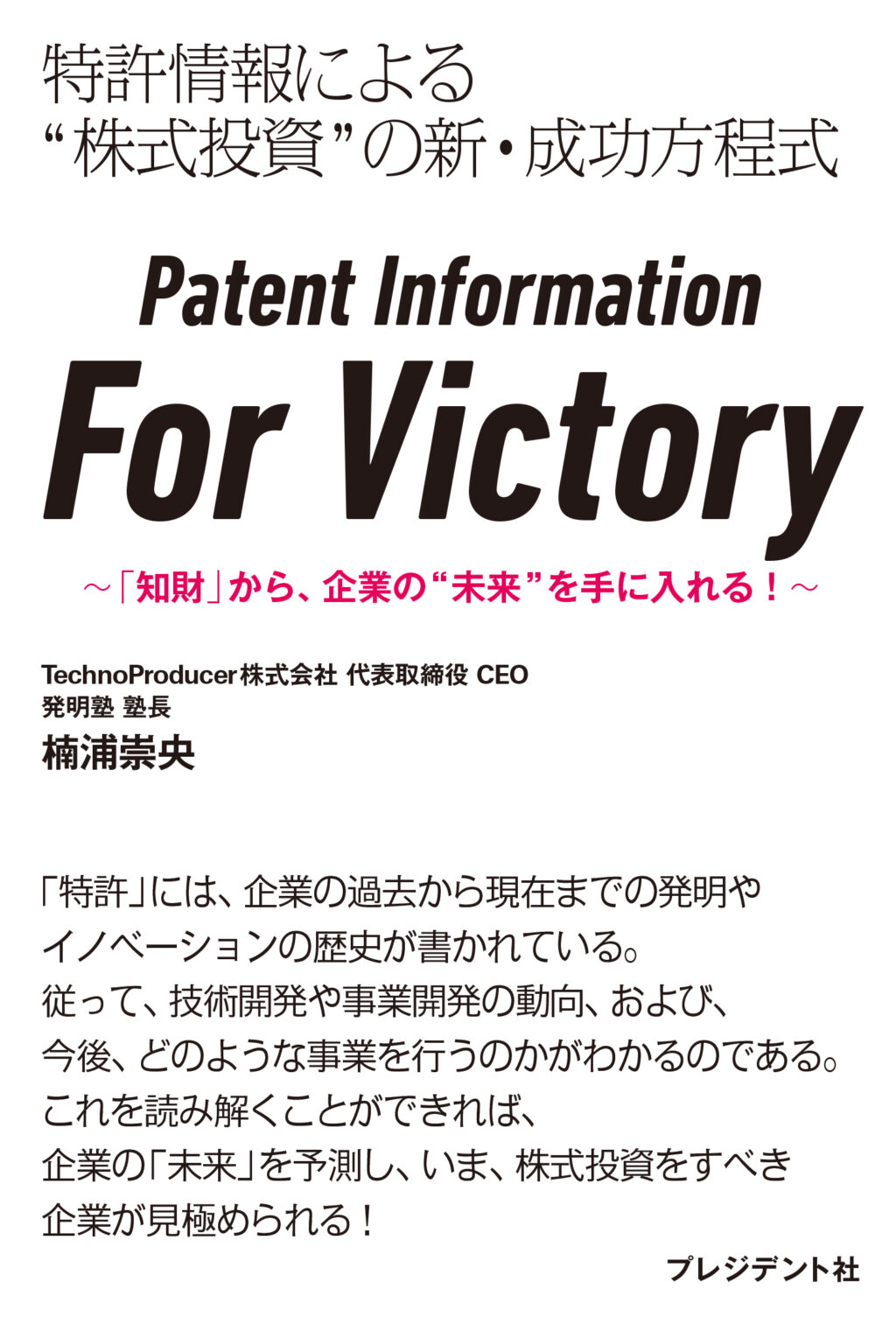
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略