「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、2024年の年末に行いました対談の概要紹介と補足になります。
対談させていただいたのは、「知財若手の会」(チザワカ)を主宰されているLeXi/Ventの上村さんです。
普段は、特許分析のお仕事をされているそうです。
「知財」から、企業の”未来”を手に入れる、その通過点「Patent Information For Victory」を語る
https://creators.spotify.com/pod/show/spkqhj4clig/episodes/Patent-Information-For-Victory-TechnoProducer-CEO---Part1-e2sjhke
この記事の内容
あまり聞かれることがなかったので話す機会もなかったのですが、今回、「知財若手の会」を主宰されている してらっしゃる上村さんとの対談なので、大学時代に学んでおいてよかったことを、お話しました。
先日のセミナーでも、大学生の方が何名かいらっしゃったからです。
大学時代に学んでおいてよかったこと。
それはずばり、「課題」なんですよね。
「課題ー解決」の、課題です。
僕は、大学時代は機械工学科に所属し、大学院では「エネルギー応用工学」専攻に所属していました。
大学院が改組になり、研究室が異動しただけなので、専門分野(金属材料の熱処理・微細組織・疲労強度の関係)は変わっていません。
当時のボスが、「これからはエネルギー問題を解決するのが使命だ」と思ったようで、寝耳に水だった同期は、研究室を全員(!)出ていきました(笑)。
つまり、同期でただ一人、研究室に残ったんです。
これって、すごくないですか?
なんで、残ったのか。
僕は、専攻の名称が変わることについてはちょっとめんどくさいなと思いつつも、「機械工学」という「シーズ」だけを学ぶことに違和感があったというか、「飽きて」いたので、「世界のエネルギー問題」という「地球規模の課題」について学べる絶好の機会だ、面白そうだな、と思っていました。
実際、大学院の講義はどれも非常に面白く、卒論や修論は20枚ぐらいしか書いてないのに、「エネルギー安全保障論」ゼミのレポートを50枚ぐらい書きました(笑)。
レポートのタイトルは、「2035年 アジア経済共同体への道」です。
ゼミのポリシーで、「40年後までのストーリーをかけ」ということでしたので、2035年になっています。
「君たちがちょうど定年退職する頃でしょ」と、教授は言っていました。
自分のキャリアを取り巻くマクロ環境がどうなるのか、しっかり考察せよ、ということなんですね。
エネルギー安全保障論のレポートとして、なぜ「アジア経済共同体」なのか。
エネルギーはインフラであり、安全保障問題に直結し、宗教や政治が絡んでくるので、技術だけでは解決できない問題が多数あったんですよね。
それを解決しつつ、発展するために「アジア経済共同体」が必要だと考え、それがいつ頃実現可能になるか、「未来予測」を行ったわけです。
内容は、当時は時代としてまだ早かったらしく、ゼミの教授は「まだまだ早いね」「でも良く分析できてる」と評価してくださいました。
ちなみにそのゼミを担当されていたのは、神田 啓治(かんだ けいじ)教授。
京都大学名誉教授、電力中央研究所名誉研究顧問で、フランス共和国国家功労勲章を受章されている、原子力工学界の偉人です。
噂では、アメリカのDARPAにも出入りされていて、安全保障の専門家だとされていました。
(秘密情報なので、先生は否定も肯定もされませんでした)
エネルギー安全保障論ゼミでは、エネルギー全般や安全保障の話だけでなく、「炉(ろ)物理」と呼ばれる原子力工学の基礎から、核燃料サイクルの実際まで、幅広く、そして深く、指導いただきました。
僕が機械工学科に残っていたら、指導いただく機会は一生なかったでしょう。
良いタイミングで、研究室が(勝手に)異動したわけです。
ラッキーですよね。人生はこういう「偶然」で、できています。
僕は、新卒で川崎重工業に入社した後、コマツへ転職して風力発電の新規事業を担当しましたが、神田先生の指導が無ければ、風力発電をやるためにコマツへ転職しようとは思わなかったでしょうね。
エネルギー問題について深く考える機会をもらえた、貴重なゼミでした。
技術はもちろんですが、安全保障や政治、社会学や哲学といった観点からエネルギー問題を考える授業などがあり、刺激的な毎日でした。
「発明の価値は、解決する課題で決まる」と、発明塾でいつもお話していますが、それにはこういう背景があるんですよね。
脱炭素だ、SDGsだ、と騒がれるはるか以前に、エネルギー問題についてみっちり学んだことは、今頃ようやく役立っていますね(笑)。
手っ取り早く儲けるなら、機械工学科に残ったほうがよかったのかも知れません(笑)。
それはそれで正解でしょう。
人生は自分次第です。
「偶然」と書きましたが、重要なことは、その「偶然」にどう対応するか、でしょうね。
拒否するもよし、乗っかるもよし。
人生は偶然の連続です。
偶然しかない、と言ってもよいかもしれませんね。
このへんは、PODCASTで、僕が遭遇した様々な「偶然」を紹介していますので、参考になれば幸いです。
転職しようとした会社の社長が、入社日の直前に突然クビになったり、自身が役員を解任されるとわかって、、、なんて、なかなか自分の意志や計画では体験できません(笑)。
振り返るとよい経験なので、皆さんも経験されるとよいな、とは思いますけどね(笑)。
それはつまり、「挑戦してください」ということです。
挑戦しない世界は、予定調和の世界ですからね。何も起きないし、どこにも行かない。
「計画的偶発性」という考え方がありますが、そんな難しい話をする必要はありません。
まず、漢字が多すぎます(笑)。
「挑戦しましょう」で、オッケーです。
名刺交換などの際に「特許」という言葉を出すと、「特許なんて意味ない」「特許を取っても売り上げはあがらない」のようなことを仰る方が、一定の割合でいます。
例えば、異業種交流会のような場で、特に顕著ですね。
こういう場合、僕は反応しません。
反論ではなく、「反応」しないんですね。
「意味ない」の定義が不明確ですし、「特許と売り上げ」についての因果関係も不明確だからです。
(業界にも依存します)
口が滑っただけの方も、いらっしゃるでしょう。
聴かなかったことにしておくほうが、全員のためなのです。
ただ稀に、僕に意見を求めてくる方もいらっしゃいます。
その場合、僕はいつも、「特許」について、ではなく「特許情報」について話すことにしています。
しかも、僕が経験したことについて、「具体論」を詳細に、お話しするんですよね。
事実は、否定できませんから。
セミナーや書籍で繰り返し紹介している通りですが、あらすじはこうです。
僕が「もうダメだろうと思ったベンチャー」のCTO兼事業責任者として、「最期の悪あがき」として特許情報を調べてみた。
「最後」ではなく、まさに「最期」という言葉がぴったりな、もう全くダメで何一つ見込みがない状態でした(笑)。
でも、CTOで事業責任者ですから、やれることは全部やろうと決めたわけですね。
2000件の特許を、クリーンルームでの実験の合間に読破し、用途の仮説を立て、見込み顧客の名簿を作成。
事業に必要なもの、それは「名簿」ですからね(笑)。
多くの方は「商品」だと思ってますが、「見込み顧客の名簿」の方が重要です(笑)。
僕は事業立ち上げに欠かせない「見込み顧客の名簿」を、「特許情報」というメディアを通じて、生み出したわけです。
なので、僕は「見込み顧客の名簿」の重要性を痛感しています。
この辺までくると、全く異業種の方でも、「特許から名簿作ったのか、それはスゴイな」「こいつナカナカやるな」と思うようです。
僕にとって、「特許に意味があるか」なんてことは、どうでもいいんですよね。
一般論では、どこにも行けないし、何の結論も出ない。
「僕には、とっても役に立ってますよ」「特許で命拾いしましたよ」というだけの話なんです。
命拾いしたら、それで十分でしょう。
僕は、それ以上のことは特許には求めていません(笑)。
命の恩人ですからね(爆笑)。
命の恩人に、もっと役に立て!というほど強欲でも恩知らずでもありません(大爆笑)。
ちなみに、以前はよく「2000件も特許を読むのは大変ですよね」とか「2000件も読めません」という意見?クレーム?をいただいたのですが、「これやらないと、半年後に確実に会社が潰れる」というところまで来たら、誰でも読めるようになります(笑)。
仕事とは、そういうものです。
スキルアップとは、そういうものです。
やるかやらないか、であって、できない、という選択肢はないのです(笑)。
上村さんが最後に、「楠浦さんにとって特許(情報)って何ですか?」という、すごくナイスな質問をしてくださっています。
僕の答えは、「独自のレンズ」です。
独自のレンズとは何か。
これは、発明塾の造語で、「その人にしかない、モノの見方、情報源、あるいは情報のフィルター」みたいなものだと思っていただければよいでしょう。
僕が「レンズ」と言ってるのは、「その場にあるんだけど、(小さすぎて/微かすぎて)見えないものが見える」ものだ、と言いたいからです。
情報分析の目的の一つが、「見えない(とされている)ものを、見ること」です。
もっと言うと、「他の人には見えないものが、自分だけに見えるようにすること」です。
そういう仕事をするのに、「特許」は欠かせないんですよね。
誰にでも見えるものを見て喜ぶのは、「観光」でしょうか(笑)。観光も大事ですけどね。
対談でお話していますが、弊社が創業した17年前は、知財部の方ですら「特許なんか1.5年前の情報で古いし、発明者は嘘ばっかり書いてるし、情報として全く使えない」とおっしゃっていました(笑)。
創業当初、弊社は特許調査分析を専門にしていました。
僕は主に、技術マーケティングを中心とした、特許情報分析の営業に毎日出かけていました。
その際、ほぼ毎日、「特許は古い情報だから使えない」と、言われていました(笑)。
営業としては失敗しているわけですが、これは、僕にとってはチャンスだったんですよね。
あれ?どこかで聞いた話ですね(笑)。
日々特許に触れているはずの知財部の方ですら、特許情報の可能性に全く気付いていない。
僕が、投資ファンドから依頼を受けた「発明」の仕事で、「アジアでトップ8」に入ることができたのには、こういう背景があったんですよね。
その後も、トップ発明家に選ばれ続けました。
誰も特許情報なんて使ってないし、使えないと思っているので、使ったら圧勝です。
そのファンドでは、年に一回、ソウルの高級ホテルで1週間缶詰めで発明合宿をやるんですよね。
世界中から、トップ発明家を集めてきて、全員で発明に取り組むという、なかなか凄まじい合宿です(笑)。
口の悪い人は、「脳みそ吸い取られる」みたいなことを言ってましたが、実際参加すると、「脳みそが増えている」感じでした。
世界のトップ発明家と一緒に、毎日毎日、一日中発明をすると、一週間でかなり賢くなります。
聞くのと、やるのとでは、大違いなんですよね。
脱線しました。
僕が、分野に関係なくその場で発明を次々と出していくと、他の発明者(海外の方です)は度肝を抜かれていました(笑)。
お前、いったい専門はなんなんだと(笑)。
機械工学の修士だというと、必ず全員、微妙な顔をしますね(笑)。
修士しか持っていないと、基本的に海外では相手にされません。
現に、僕以外は全員ドクターかMBAとのダブルディグリーです。
でも、残念ながら、発明は学位ではなく実力主義の世界です(笑)。
専門知識があっても、発明が出せなければお役御免で、誰にも相手にされません。
厳しい世界です。
あと、「僕の専門とは違いますのでノーアイデアです」も許されないんですよね。
ソウルまで来て、何を寝言をいうてるんやと(笑)。
関西弁では、「お前、のこのことここまで来て、いまさら何眠たいこと言うとるねん」って感じです。
そんなことはどうでもええから、サッサとアイデア出せ、仕事やぞ、ということですね。
一週間、日替わりでありとあらゆる分野の発明に取り組みます。(取り組まされます、が正しい)
今日は半導体材料、明日はIoT、その次は食品、医療機器、エネルギー関連、建築、リサイクル、ロボット、EV、無線通信、、、みたいな感じです。
ほんとに、何でもありなんですよね。
未来を丸ごと予測しよう、それを全部知財で押さえよう、みたいな場でした。
そこで、全員の信頼を勝ち取るには、ずば抜けたアイデアを、分野を問わず出し続けるしかない。
議論は英語なので、日本語ボケしている僕には不利です(笑)。
その分、良いアイデアを出して、議論に割って入る必要があるんですよね。
毎日毎日、分野関係なく良いアイデアを出し続けられたのには、ちょっとした「からくり」があります(笑)。
簡単なことです。
弊社は当時、また特許調査と分析を受託していたのですが、僕といつも組んで仕事をして、僕の情報分析の好みを知り尽くしている、「Tさん」というベテランの特許分析スタッフが一名いまた。
一日の発明セッションが終わって、夜、ホテルの居室に戻ると、Tさんにメールするんですね。
「明日のテーマはXXらしいので、明日朝までにこの分野の特許をいつものパターンで分析してレポートしてください」と。
次の日、その分析結果を見ながら、その場でさらに調査しつつアイデアを出していくんです。
そのレポートにある情報とそこから出せる仮説(僕のアイデア)を周りの発明者と共有し、アイデアと情報をもらいながら、一緒に考えていく感じですね。
これって、今でいう「IPランドスケープ」ですよね(笑)。
僕は、IPランドスケープのおかげで、世界のトップ発明家として、勝負し続けられたわけです。
まさに「Patent Information For Victory」(特許情報で勝つ!)ですね。
「独自のレンズ」とはそういうことなんですよね。
おかげで、一緒に発明を出した、工学博士で連続起業家、起業した会社をナスダックに2社上場させたイスラエル人発明家に、「クスウラさん、なかなかオモロいね」と言ってもらえました。
彼はいい奴ですね(笑)。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
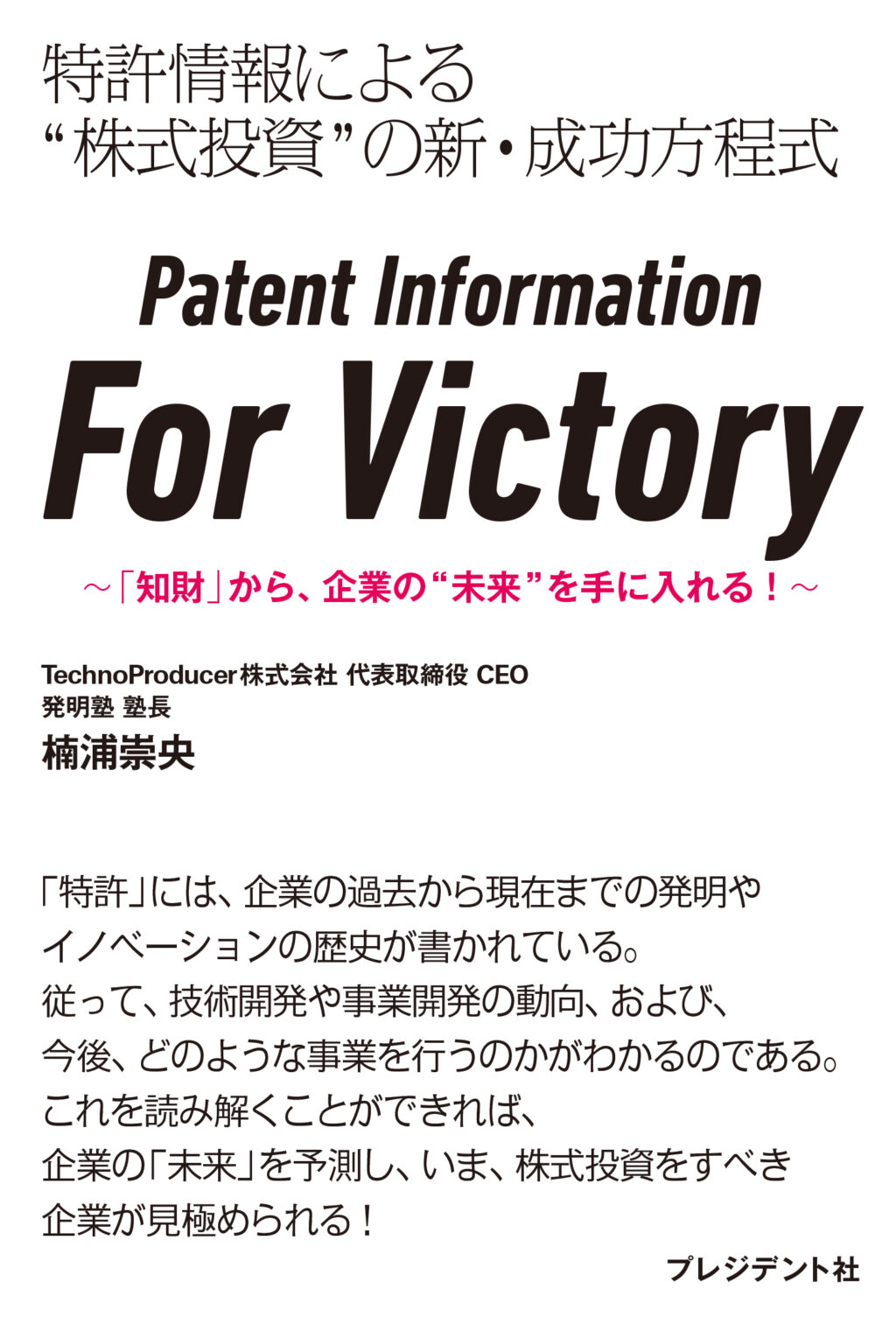
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略