【要約】
「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、2025年4月に開講し討議を行った「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)」の第5回ワークショップの振り返りです。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)
これまでの振り返りは以下のコラムをご覧ください。
第1回振り返り:新規事業支援者の心得とは? 成功する提案を導く支援の本質と実践法
第2回振り返り:新規事業「支援者」と「指導者」の違い|たった1回の指導でここまで変わる! 成果を出す支援者育成の本質
第3回振り返り:決断力を育てる新規事業支援|「頭がちぎれるほど考えたか?」で成果を変える
第4回振り返り:“チラシ思考”で動かす新規事業企画|支援者が築くエコノミック・モートと決断支援の技術
第4回~第5回の間の振り返り:支援者は“育つ”|新規事業支援に必要なメタ認知と振り返りの力
第3回と第4回は、「企画」を検討する段階です。
「確信犯になっていただく」時間ですね。
支援者は、提案者が確信犯になれるように、支援をしていくわけです。
第5回と第6回は、「企画提案書」の作成を進めます。
実は「企画」と「企画書」は、全く別物なんですよね。
だから、「企画」ができたら、再度ゼロベースで「企画書」を考えていきます。
自身が検討した「企画」の延長で「企画書」を作ると、「確実に社長・役員が寝てしまう」企画書が出来上がります(笑)。
そういう企画書、企画プレゼンは世に結構多いのですが、僕でも寝てしまうぐらいの「強力な睡眠薬」になります(笑)。
では、本題へ。
第5回の討議は、提案者によるスライド草案の発表と、それに対する支援者からのフィードバックが中心でした。
提案者の側から見ると、「エッジ情報」→「アイデア」→「企画」→「企画書」と進む、最終段階です。
支援者の側から見ると、「最先端情報の提供」→「ちょうどよい先行例の提供」(独自性・独占の確認)→「ロジック構築」(売れる・勝てる・儲かる・できそう・おもろい)→「伝え方の工夫」 になりますね。
僕がコメントした内容を、3点に絞って挙げておきます。
支援者が最低限やらないといけないこと、ですね。
① スライド単位でロジックチェック
② 事実と仮説を明確に
③ “役員が3枚目までに寝る” 構成を避ける
これをやると、1時間から1.5時間はあっという間です。
僕が特に強調したのは、「社長・役員はすぐに寝る」ということです(笑)。
これが正しいんですよね。
今は、何かのハラスメントになる可能性もあるので「つまらない」と面と向かってと言うことができない時代ですし、そもそも社長と役員の時間と頭脳は希少資源です。
僕の友人で、つまらない話はすぐに意識が遠のく人がいて、こいつ失礼な奴やな、と思っていましたが、話を聞くと、ご両親がある企業の役員だとのこと。
「あぁ、これが英才教育か」と感動しました(笑)。
さて、第6回に向けての作業は、だいたいいつも、以下になります。
今回もそうでした。
提案者:
支援者:
企業内発明塾は間が2週間ですが、新規事業サポーター養成講座(公開講座)は間を1週間にしましたので、非常にタイトなスケジュールです。
支援者の積極的な関与が重要になりますね。
ここまでくると、「おせっかい気味」でもよいので、巻き取っていくことが重要です。
企業内発明塾では、6回の討議(ワークショップ/壁打ち)を行って、新規事業アイデアの探索、創出から企画提案に結びつけます。
各自の進捗次第で、その通りにならない場合も多いですが、理想的には、以下のような段階(フェーズ)に分けられます。
① フェーズ1 : 情報調査とアイデア出し(第1回~第2回)
② フェーズ2 : 確信犯になるための企画検討(第3回~第4回)
③ フェーズ3 : 企画を通すための企画提案書作成(第5回~第6回)
フェーズ1の第1回から第2回では、支援者は、エッジ情報と呼ばれる最先端情報をどんどん提供し、発散させる、発想支援を行います。提案者の着眼点に共感を示しつつ、さらなる飛躍を生み出す「下駄」や「刺激」を提供するわけですね。
ただ、ここで「誘導尋問」になってはいけないという話は、過去配信のコラムの通りです。
フェーズ2の第3回から第4回では、確信犯になるための企画検討を行ってもらいます。ここでは、支援者は「売れる・勝てる・儲かる・できそう」を満たせるように「アイデアを企画へ育てていく」役割を担います。
新規事業企画書の書き方と成功事例【見本あり】 ~3つの視点で事業の魅力を伝える
https://www.techno-producer.com/column/how-to-write-innovation-proposal/
ここでも、ヒントになる情報の提供は非常に重要です。
だから、前半は「調査」「情報分析」がメインになりますね。
とにかく、瞬時に関連情報を見つけて出せる人、が支援者として求められるということです。
一般論ではなく、ニッチな最先端情報が欲しいので、知識と検索スキルの両方が必要になります。
フェーズ3の第5回から第6回では、社長・役員が必ずOKする(であろう)企画提案書を作ります。
「寝ない」というのは、その最低ラインの話ですね。
提案書のロジックチェック、ファクトチェックはもちろんですが、プレゼン技術含めた「表現技術」の支援が重要になります。
企業内発明塾では、不慣れな方、自信がない方については、プレゼン練習を動画に収めてもらって、楠浦がチェックする場合もあります。
「必ず通す」ためにやるべきことは、すべてやるのが「企業内発明塾」です。
次回以降、全体の振り返りを行いますが、いったんここまでの振り返りを兼ねて、そもそも「支援者に求められることは何か」を、言語化しておきます。
これは、企業内発明塾でも、質問があれば答えている内容です。
企業内発明塾では、主役は提案者なので、余計なことは話さないようにしています。
提案者が混乱する可能性があることと、そもそも時間がもったいないからです。
その場に6名いるとして、僕が5分話すと30分のロスですからね。
① 完璧より即応
② 巻き取る・寄り添う
企業内発明塾参加者であれば、僕が何をしていたか、振り返ると理解できると思います。
意外と皆さんができないのは、これですね。
”提案者の「動き出した勢い」を止めないこと”
意外なことに、止める方が非常に多い。
でもそれだと、相手の力が使えなくなります。
相手の力をうまく使いながら、理想の状態を目指す。
これが発明塾の考え方です。
だから、相手の頭脳を止めない支援が重要。
もっと回転させて、もっともっと、いい情報、いいアイデア、いい企画にたどり着いてもらう。
これしかないんですよね。
こちらから「弾」をぶつけていって、「はずみ車」をどんどん回す。
早く結論を出してもらう。
運動量保存則であり、運動エネルギー保存則なんですよね。
相手を止めようとすると、こちらも無駄なエネルギーを使うのに、全体として停滞してしまう。
動かないと結果は出ません。
最悪ですよね。
繰り返しですが、支援とは「指導」ではなく、「共同でアイデアを育てる」ことなんです。
支援者は、提案者の不安や迷いに寄り添いながら、時に前に出てロジックを整え、資料を磨き、伝わる形に昇華させる役割を担います。
実は、今回の「新規事業サポーター養成講座(公開講座)」で検討している企画は、全体としてはかなり壮大な企画になっています。
これは、また別途セミナーなどでお披露目できる機会があると思います。
(開催条件として、検討内容はすべて教材等に活用できることにしています)
ですので、情報の交通整理だけでも、結構大変です。
以前に書いたかもしれませんが、ある段階で、僕がいったん優先度をつけて、内容を絞り込んでいます。
それをしないと、情報におぼれて、進まなくなるなと感じたからです。
これは「指導者」的な支援でしょうね。
いずれにせよ、提案者の孤独な構想に光を当てるのが、支援者の仕事です。
時と場合によっては、「どこに光を当てるのか」という決断も必要になる、ということです。
ただ、これは上級編ですね。
新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)
https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/
(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
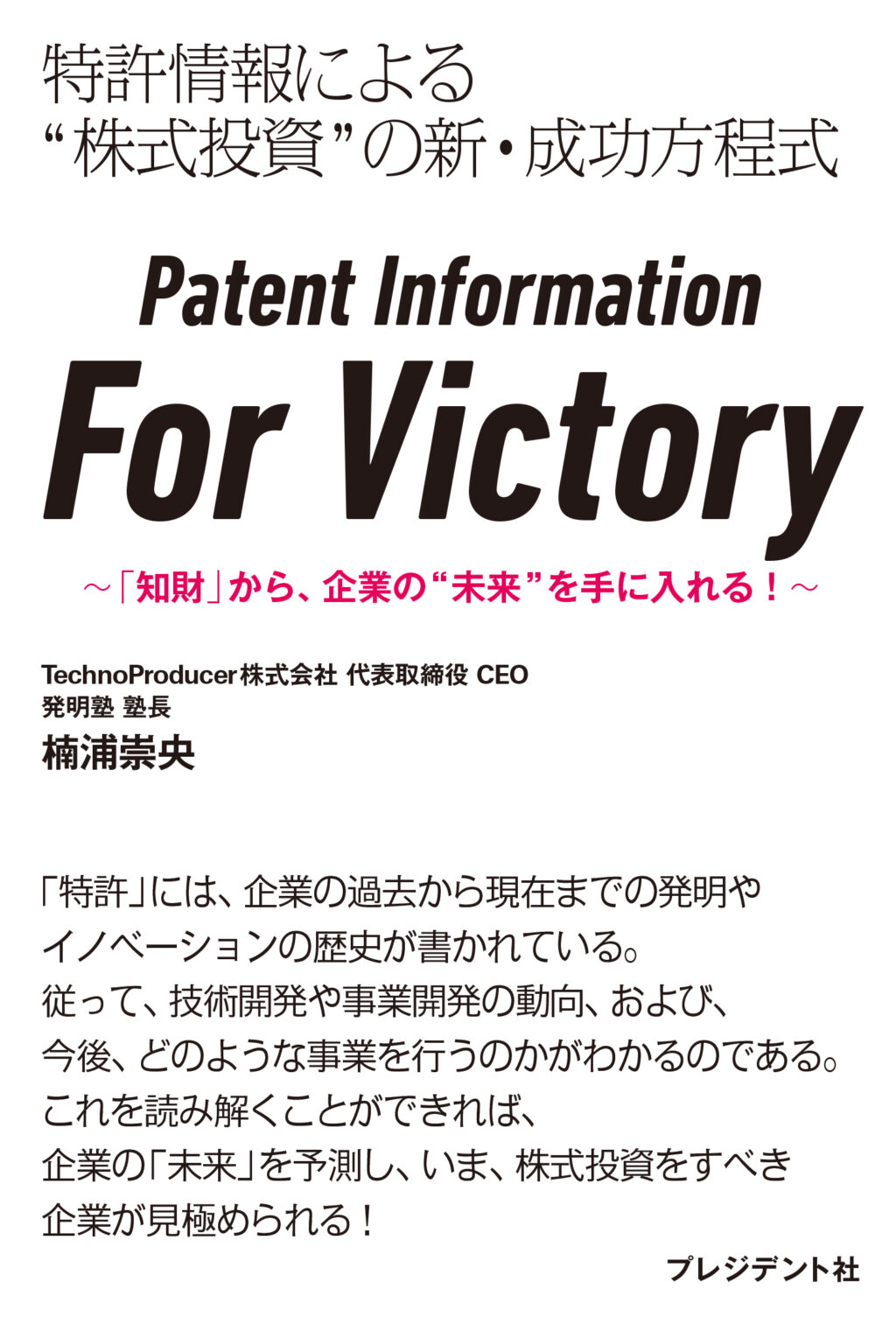
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略