「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、2024年12月6日(金)に開催したセミナー「研究シーズから事業化へのストーリーを描く方法 ~サイエンスと産業のギャップを埋めた実例から学ぶ」の報告、第3弾です。
事後アンケートでいただいたご質問と、追川様からのご回答の紹介、および僕からの補足です。
今回も、なかなか興味深いご質問です。
発明塾セミナー「研究シーズから事業化へのストーリーを描く方法 ~サイエンスと産業のギャップを埋めた実例から学ぶ~」(セミナーは終了しています)
https://www.techno-producer.com/news/seminar-research-to-business/
セミナー動画販売は以下↓
https://e-hatsumeijuku.techno-producer.com/research-to-business
この記事の内容
【ご質問】
大学は個の研究者の集まりなこともあり、全体としての知財ポートフォリオを作りにくい、と感じています。そんななか、何ができるのか何かアドバイスをお願いしたいです。
なかなか興味深い質問ですね。
そもそも、「大学全体として知財ポートフォリオを管理すべきなのか」という点も含め、議論の余地があるところだと感じました。
僕の考え、あるいは経験について、最後に書きます。
【追川様の回答】
これは極めて重要な質問だと思います。まず、大学が様々な研究を抱えている中で、全体としてのポートフォリオを考えるのは実務上非常に難しいと思います。現実的な解は、一つ一つの研究室の特許を時系列でしっかりと管理することと、研究領域が似ていたり、協力していたりする研究室の集合を把握しておくことだと思います。
また、大学の場合、基本特許は取るけれど、コスト制約からアプリケーションの特許は取らない傾向があります。バイオや薬は基本特許だけというのはあり得ますが、物理工学系・材料工学系ではスタートアップを作ったり、企業への移転したりするためには、アプリケーションの特許も考える必要があると思います。闇雲に特許を出すのはコスト面で無理なので、良いアプリケーションを絞るために発明塾の手法がよく嵌ると思います。
最後に、最近は若手研究者の任期が短いため、5年程度で異動してしまうケースがあります。そうなると有望な研究に基づく特許が異なる機関に分散して、ポートフォリオ化できなくなります。これは人事制度の問題なので、そう簡単には解決しないでしょう。
わかりやすいですね。
実際に大学にいらっしゃった経験を踏まえ、「大学全体としてのポートフォリオ管理は難しい、したがって、まずは個別の研究(室)のポートフォリオ管理をする」のがよい、とのこと。
王道ですね。
一方で、研究領域が似ていたり、協力関係にある研究室の集合を把握しておく、とおっしゃっています。
これは、面白い視点ですね。
また、「良いアプリケーションの特許を取っておくこと」を挙げておられます。
発明塾の手法はここで使えるだろう、とのコメントもあります。
ERATO/東北大でのプロジェクトの経験を踏まえ、ということでしょうか。ありがとうございます。
研究者の移動に伴う知財の分散化の問題は、大学だけでなく、研究者も苦しめているように、僕は感じます。
何がボトルネックなのか把握できていませんが、何とかして欲しい気がするので、実際に僕が経験した事例について、この後、書ける範囲で書いておきます。
大学の知財戦略について、工夫の余地がありそうだなということで、少し僕の経験談を書きます。
何とかなりませんかね、という今後に向けた問題提起ですので、関係者の方は、ご理解ください。
少し前の話ですが、ある大学の先生の研究内容を事業化したい、ということで僕に相談が来ました。
「楠浦さんなら、この分野は詳しいですよね」ということだったようです。
(僕が詳しい分野は多岐にわたるので、何の分野か、わかる人は居ないと思います)
研究内容としてはほぼ実用化レベルに達しており、技術移転を含めた事業化はさほど難しい話ではないな、と思ったのですが、さすが、僕に相談が来るだけあって、いろいろ困難を極める点がありました(笑)。
駆け込み寺的に、素晴らしく難しい仕事が来るのが、最近の傾向です(笑)。
では、何がどう難しかったか。
一つは、先生が大学を異動されたことで、知財(権)が分散していること。
これに、共同研究先との権利関係が加わって、知財(権)を軸に事業化や技術移転を行うことは、常人には不可能でした。
こういう時に重要なことは、「何が売れるのか」を考え抜くことなんですよね。
「自分たち(だけ)が持っていて、相手が絶対に持っていない」と言えるものが何か、徹底的に調べ上げることから始めました。
詳細は話せませんが、ある「素材」に関する技術が浮かび上がりました。
通常、材料も分析すれば大概わかるのですが、この分野なら、リバースエンジニアリングはまず不可能だ、と言える点が僕には明確にわかりました。
(これも、僕の専門分野でした)
ただ、こういうものを売るのは非常に難しいんですよね。
言うと内容がばれてしまいますので言えないのですが、言わないと価値は伝わらない。
NDAを結んでいようが何をしようが、ばれたら終わりです。
「ばれたら最後なので、これだけは絶対に言わない」という線を、関係者間で明確に決めての交渉を、何か月もやりました。
何でもいい、というのは言い過ぎですが、やはり、ある程度のものが「権利化」されて「集約」されていると強いんですよね。
相手がお金を払う理由が、明確に出てきますので。
事業化、実用化のハードルが、ぐっと下がります。
それは「大学」という単位が良いのか、「個人」単位が良いのか。
立場によって、意見は割れそうですね。
質問の中では、「大学としての知財ポートフォリオ」の話が出ていました。
それはそれで、とても大事だと思います。
でも、むしろ僕は、大学の「知」を円滑に事業化する、実用化する、「マネタイズする」ためには、「研究者単位での知財ポートフォリオ」が、「現場レベル」では大事なんじゃないかな、という所感を持ちました。
大学の知を本気で事業化しよう、実用化しよう、という「志がある偉い方」には、ご一考いただきたいところです。
もちろん、制度が整備されるのを待っていられませんので、「現場」(僕たちのレベル)では、あの手この手で、ある種の「非常識なテクニック」を駆使して、やっていくわけですけれども。
おかげで「そんな手があるのか!」というような、いろいろな手を思いつきました(笑)。
僕には勉強になりましたし、「困難な状況を打破できるテクニック」のレパートリーが増えてうれしい(笑)のですが、研究者、および、各大学にとって、現状は明らかにマイナスなんでしょうね。
どうしようもなく行き詰っているんだけど、どうしても何とかしたい、という案件があれば、ぜひご相談くださいませ(笑)。
僕の人生は、それを何とかする、そこ(マイナス)から大成功させる、の連続です(笑)。
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
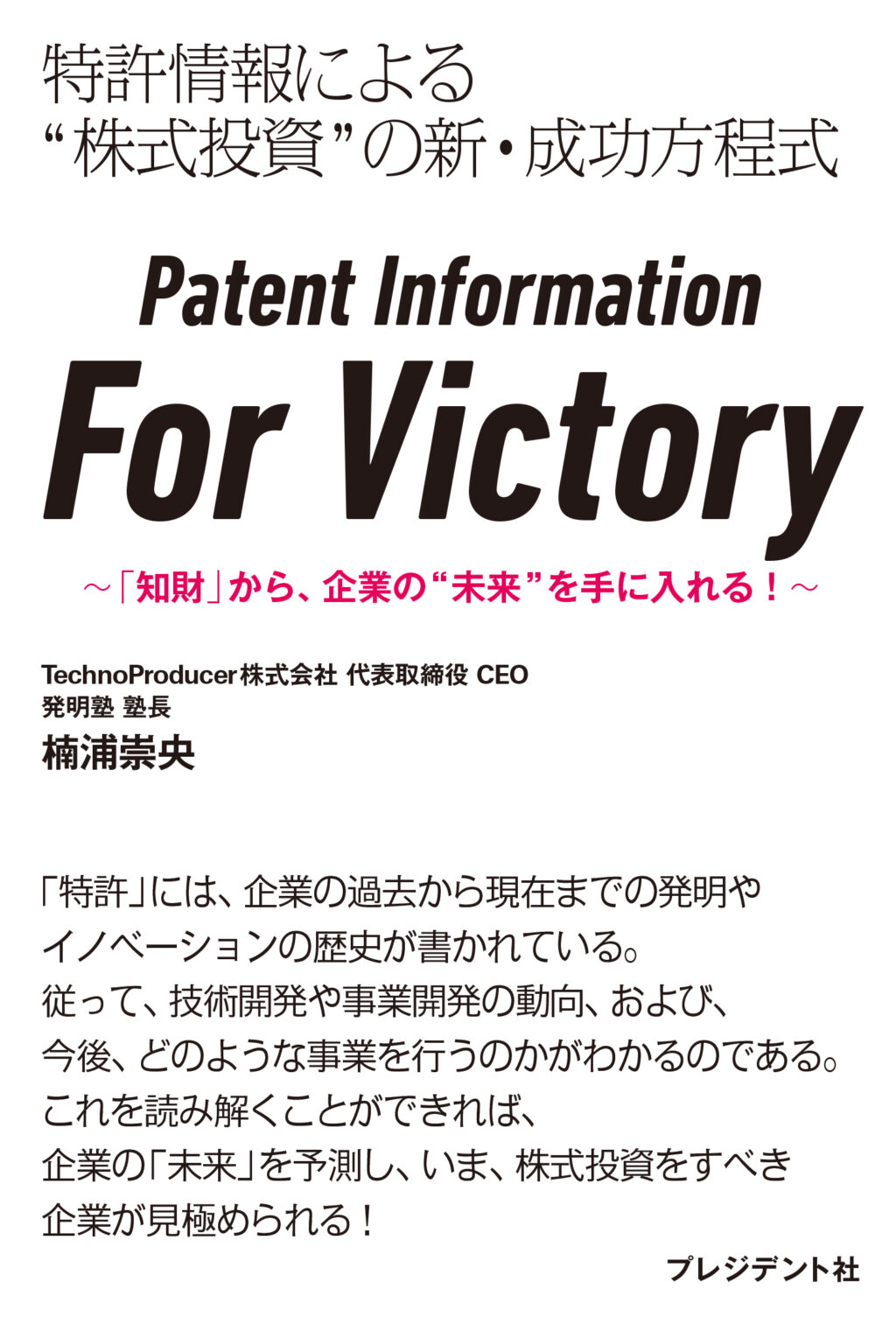
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略