「発明塾」塾長の楠浦です。
今回は、「エッジ情報」として旭化成の無形資産戦略を取り上げます。
それってエッジなの?と思われる方もいるでしょうか。
取り上げる理由の一つは、2024年の年末以降、「旭化成の無形資産戦略について、どう思いますか」という質問を、イベントなどでお会いした方から何度かいただいたことです。
そろそろ回答しておきたい、ということですね(笑)。
また弊社は知財に関するサービスを提供していますので、「知財戦略」という視点から、旭化成の無形資産戦略について、整理しておきたいと思っていました。
以前からコツコツ調べていた内容を精査した結果、多くの企業の方、特に製造業の方々には参考になる点が多いと感じましたので、エッジ情報の一つとして、僕の理解と意見を配信します。
この記事の内容
無形資産って何でしょうか? 企業の資産というと、土地や機械設備のようなものを思い浮かべる方がいらっしゃるでしょう。これらは有形資産といいます。目に見えて形があるものですね。
一方、企業には、知識、スキル、知的財産、デジタルインフラなど、目に見えない資産があります。これが無形資産です。
無形資産は、企業価値の源泉として重要性を増している、とよく言われますね。
例えば、いわゆるメーカーにお勤めの方であれば、現場の製造ノウハウや、それをデジタル化したシステムが競争優位性と持続可能な成長の鍵となっていることを、日々実感されているでしょう。
化学メーカー大手の旭化成株式会社(旭化成)は、無形資産の一つである「知財」(知的財産)に関する活動で有名な企業です。
旭化成は現在、技術、知的財産、人材、デジタル能力といった多様な無形資産を活用し、事業モデルの転換を推進している、とIR情報で宣言しています。
「無形資産を活用した事業モデルの転換」って、いったいなんでしょうね。とっても気になります。
ここでは旭化成の無形資産戦略、無形資産を積極的に活用した事業の内容、ビジネスモデル、具体的事例を紹介します。
旭化成は、2024年12月17日のプレスリリースで、現在、無形資産を活用したビジネスモデルの変革や新事業創出に力を入れている、としています。
これは、2024年度が最終年度になる中期経営計画の重点テーマの一つが「無形資産の最大活用」であることを踏まえたもの、ということのようです。
旭化成のプレスリリース:2024年「無形資産戦略説明会」を開催
https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2024/ze241217.html
また旭化成は、2024年12月13日に「無形資産戦略説明会」を開催し、無形資産を活用した事業戦略について、具体例をあげて紹介しているのですが、資料のサブタイトルが「無形資産が価値の中心となるビジネスモデルの強化」なんですよね。
これ、当たり前のような気もしますが、製造業のど真ん中、化学メーカーとしてどう取り組んでいるのか、非常に気になりますよね。
あと「強化」と書いているので、「これまでもやってるけど、もっと力を入れるよー」という宣言だと、僕は捉えました。
資料を見ると、経営課題として「効率性の向上」をあげています。ROIC(投下資本利益率:ロイック)ですね。
ROICは、簡単に言うと「事業に必要なお金がいくらで、それでどれぐらい儲かったか」を示す指標です。
石油化学系の企業は、事業に大規模なプラントが必要だったりして、お金がかかります。したがって、どうしてもROICが低くなりがちですが、そこにメスを入れるということでしょう。
ROIC向上のための方針として、以下3点をあげています。
・スピード
・アセットライト
・高付加価値
この方針をブレークダウンして、「従来の製品、サービスに加えて、無形資産が価値の中心となるビジネスモデルの構築」とあります。
具体的には「さまざまな無形資産から生み出されるソリューション、ライセンスパッケージ」を提供していくようです。
旭化成がイメージする「ソリューション」「ライセンスパッケージ」とは、具体的にどのようなものか。順に見ていきましょう。
旭化成の無形資産戦略、つまり無形資産を活用した事業戦略の1つ目が「ソリューション」型事業です。
旭化成が考える「ソリューション」って、具体的にはどのようなものか。
資料では、ソリューション型事業の例として、「①自動車内装材事業」「②イオン交換膜法食塩電解事業」「③クリティカルケア事業」「④海外住宅事業」があげられています。
例えば1つ目の自動車内装材事業では、2018年に買収した「Sage Automotive」を軸に「プラットフォーマー」になる、としています。
これは「素材」を売り込むのではなく、「顧客(自動車メーカー)が実現したい内装を、多様な素材と後加工(意匠)技術で実現する」ことを指しているのでしょう。まさにソリューションですね。
ジョブ理論でいうと、顧客がほしいのは「車内の雰囲気」(価値)であって、「人工皮革」(素材)ではない、という感じですね。とってもかりやすいです。
これに関連した動きとして、従来から旭化成が保有している素材のブランドの一部を廃止し、新たに買収したSage社のブランドに統一しています。
「ブランドを買った」つまり「顧客の認知」という無形資産を買った側面もあるのでしょう。
メーカーとしては、思い切った判断のようにも思えますが、まさに「無形資産を優先する」取り組みだと感じます。
自社の無形資産にこだわらず、「無形資産の価値を最大化する」ためにどうすべきか、を考えているのでしょう。
自社の資産と他者(社)の資産。有形資産と無形資産。この2軸ですね。
そもそも自動車自体が、「モノ」としての価値以上に、「ファッション」「ブランド」の価値が大きくなっていますから、当然の動きなのでしょう。
車は安全快適に走れれば良いと考えている僕でも、「この車のニューモデルはレカロのシートですよ!」と言われると、「レカロ」という言葉につい反応してしまいます(笑)。
ちなみにレカロは、レース用の車などでよく使われるシート(座席)のメーカーでありブランドです。
技術に裏付けられたブランドの価値を、どう活用するか。
化学系企業のような製造業ど真ん中の企業では、ブランドという無形資産でもまだまだやれることがある、という好例だと思いました。
2つ目の「イオン交換膜法食塩電解事業」では、装置や部材だけでなく、モニタリングによる予知保全などもサービスとして提供しています。これも、買収により実現していますね。
今後は電解による水素製造事業にも応用していくとのことで、楽しみです。
3つ目の「クリティカルケア事業」では、LifeVestという着用型の除細動器(心停止の方を救う医療機器)のビジネスモデルを他に転用するためスタートアップ企業に出資しています。
これは、そもそも元になる LifeVest の事業を買収で手に入れているので、買収して手に入れた事業とそこで得た無形資産を、さらに応用して事業をどんどん拡大していく、というシナリオですね。頼もしいです。
4つ目の「海外住宅事業」では、米国で住宅施工会社を買収し、住宅ビルダー(住宅建築の元請け会社)に対して配管・基礎・躯体(住宅の骨組みなど)・空調・電気を一括で提供する「プラットフォーム」ビジネスを展開しています。
ここでは、工事の進捗管理も住宅ビルダーに代わって請け負い、納期を短縮し、確実に守る、という「価値」を提供しています。いろんな業者(企業)が入る工事って、遅れがちですからね。本質、つまり、解決している顧客の「非・不・負」はこのあたりにありそうですね。
こうやって見てみると、ソリューション型事業を進めるに際し、「買収」「出資」で外部の力を借りる、取り込むことで、スピードを追求していることがわかります。自分たちの強みを「早く」成果に結びつけるために、外部の力を借りるわけですね。非常にわかりやすいです。
ROIC向上のための3つのポイントの最初に「スピード」が来ているわけですから、当然ですね。
旭化成の無形資産戦略の2つ目は「ライセンス」型事業です。
旭化成が考える「ライセンス」とは、具体的にどのようなものか。
実は、旭化成は既にライセンス型事業で実績を出しています。CO2を原料とした化学素材の生産プロセスを世界の化学メーカーに提供しているんですね。
具体的には、リチウムイオン電池の電解液の原料や、ポリカーボネートと呼ばれる光学樹脂材料をCO2から作る技術を提供し、世界中でCO2削減に貢献しています。
資料に「XX億円の収益があります」ではなく、「XX万トンのCO2削減です」と書かれているのが、いろいろな意味で気になります。
このような成功事例を踏まえ、旭化成は今後、ライセンス型事業を「TBC:Technology value Business Creation(テクノロジーバリュー事業開発)」と呼んで、加速させるとのこと。
特許・データ・ノウハウ・アルゴリズムなどについて、ライセンスに限定せず、事業移転など「ベストオーナーシップを追求した事業化」を行うとしています。
最近この「ベストオーナー」という言葉、よく聞きますね。「価値を最大化できる人(企業)が誰か」ということなんでしょうね。
自分たちがやるよりも、誰かにやってもらったほうが「顧客・社会も、自社も、相手も」得するという、三方よし的な視点ですね。
TBCの具体例として、LiC(リチウムイオンキャパシタ)技術の収益化があります。
旭化成は現在、LiCの容量を1.3倍にできる技術の特許、および技術ノウハウのライセンスパッケージを、複数社に提供しています。
R&D段階からの収益化を目指すとのことで、ここも「アセットライト」、つまり資産を持たず、「スピード」感を持って収益化する流れですね。
資料には「顧客との事業共創を加速するDX基盤」とあり、これが気になるところです。
TBCのもうひとつの具体例として、超イオン伝導性LIB電解液技術の収益化も挙げられます。
こちらは、高いイオン伝導性を持つ新たな電解液技術の知財群を基に、電池メーカーと共同開発を通じて、新規事業化していくとのこと。既に電池メーカーとともに概念実証(PoC)を完了しています。
既に実績があり、現在進行系の案件もある。
2030年に100億円から200億円の売上を見込んでいるとのこと。今後が楽しみですね。
ここまで、旭化成の無形資産戦略の考え方と具体例を見てきました。
現在保有している無形資産を、素早く(スピード)効率よく(アセットライト)活用して利益に結びつけ、経営効率(ROIC)を向上させる。わかりやすく言うと、こういう感じかなと思いました。
では、その先はどうなるのか。
企業の成長は、利益の再投資によって実現されます。つまり、「次の無形資産への投資はどうなってるの」ということが、気になりますね。R&D投資の方向性を確認しておきましょう。
2030年までのテーマとして、先ほど取り上げた「CO2を活用した素材製造」「Liイオン電池」が挙げられています。では、その次はどうか。
2040年までのテーマは、以下のとおりです。
・パワー半導体、UVレーザーなどの「ウルトラワイドバンドギャップ半導体」
・セルロースやリサイクルなど「サステナブルポリマー」
・バイオ原料による「サステナブルケミストリー」
・水素製造
・膜システムを利用した「バイオプロセス」
膜システムを利用したバイオプロセス、というのはわかりにくいですが、既にバイオ医薬企業と共同で、ペプチド医薬の濃縮システムを開発済みです。ペプチド医薬の製造期間が短縮できるとのこと。
知財戦略はどうでしょうか。
まず、そもそもどのような領域を攻めるべきかを、「IPランドスケープ」と呼ばれる知財情報を交えた情報分析により、導き出しています。これは、知財業界では有名ですね。
また、「ソリューション」に直結するDX関連の特許出願を増やしているとのことで、先の食塩電解に関する特許などを見ると、モニタリングに関する出願がありました。
そうやって生み出された無形資産のライセンスも、グローバルで積極的に行っているとのこと。
従来のような「事業の自由を確保する」ための知財活動ではなく、「事業創出」「マネタイズ」のための知財活動に、力を入れてますよ、ということですね。
最後に、「無形資産」戦略の鍵になる人材(人財)に関する取り組みを見ておきましょう。
現在、旭化成の採用の約半数は「キャリア採用」だそうです。多業種から、高度な知識やスキルを持った即戦力人材を採用している、とあります。これも無形資産の取り込みですよね。
「社外の知見と新しい価値観で革新を促す」とあります。
また、「人材の組み合わせ」にも注目しているようで、成功事例が挙げられています。
例えば、自動車内装材事業では、買収したSageの「プラットフォームビジネスのプロ」と、旭化成の繊維事業で長く経験を積んで技術と顧客をよく理解している人材の組み合わせが、顧客開拓の一つの成功要因になったとしています。
人材獲得のためにM&Aを行うというのはよく聞く話ですが、一方でPMI(買収後の経営統合)に失敗した、苦労している、という話もよく聞きます。このノウハウも無形資産ですね。
異なる能力を持つ尖った人材をどう組み合わせるか。
実は、無形資産戦略の中で最も重要な部分なのではないか、と思いましたが、あまり記載はありません(笑)。まぁ、秘密(ノウハウ)なんでしょうね。
機会があれば、投資家の立場でぜひ伺ってみたいところです。
いかがでしたか?
IPランドスケープなど、知財に関する活動で最先端を開拓してきた旭化成が、「無形資産戦略」の説明会を行った、というニュースを見たのが昨年(2024年)の12月でした。
その後、多忙により突っ込んだ調査と考察ができていませんでしたが、何名かの方から、「旭化成の無形資産戦略って、どう思いますか?」と聞かれたこともあり、その都度少しずつ調べていました。今回は、そのまとめですね。
無形資産の活用について、ここまで突っ込んだ発表(説明)をしている企業は、少なくとも日本に無いように思います。
「石油化学」事業も持っている製造業ど真ん中の企業として、なかなか頑張ってるな、応援したいなと感じました。
弊社のような、無形資産だけで事業を行っている企業から見ても、「なるほどそういうやり方もあるよね」という気付きがいくつもありましたので、皆さんにとっても、気づきの多い取り組みであり、発表・資料だと思います。
技術・知財・新規事業、そして、人材育成などに、ぜひご活用ください。
ご感想なども、メールなどでお寄せくださると嬉しいです。
ちなみに今回、無形資産戦略説明会より前に行われた、知財戦略に関する説明会の資料も熟読したのですが、こちらも非常に気づきの多い資料でした。別の機会に、紹介したいと思います。
旭化成の無形資産戦略の概要
具体事例で見る「ソリューション」「ライセンス」事業の収益モデル
楠浦 拝
★本記事と関連した弊社サービス
①企業内発明塾®
「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。
例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。
➁無料メールマガジン「e発明塾通信」
材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。
「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。
★弊社書籍の紹介
①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。
Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用
➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!
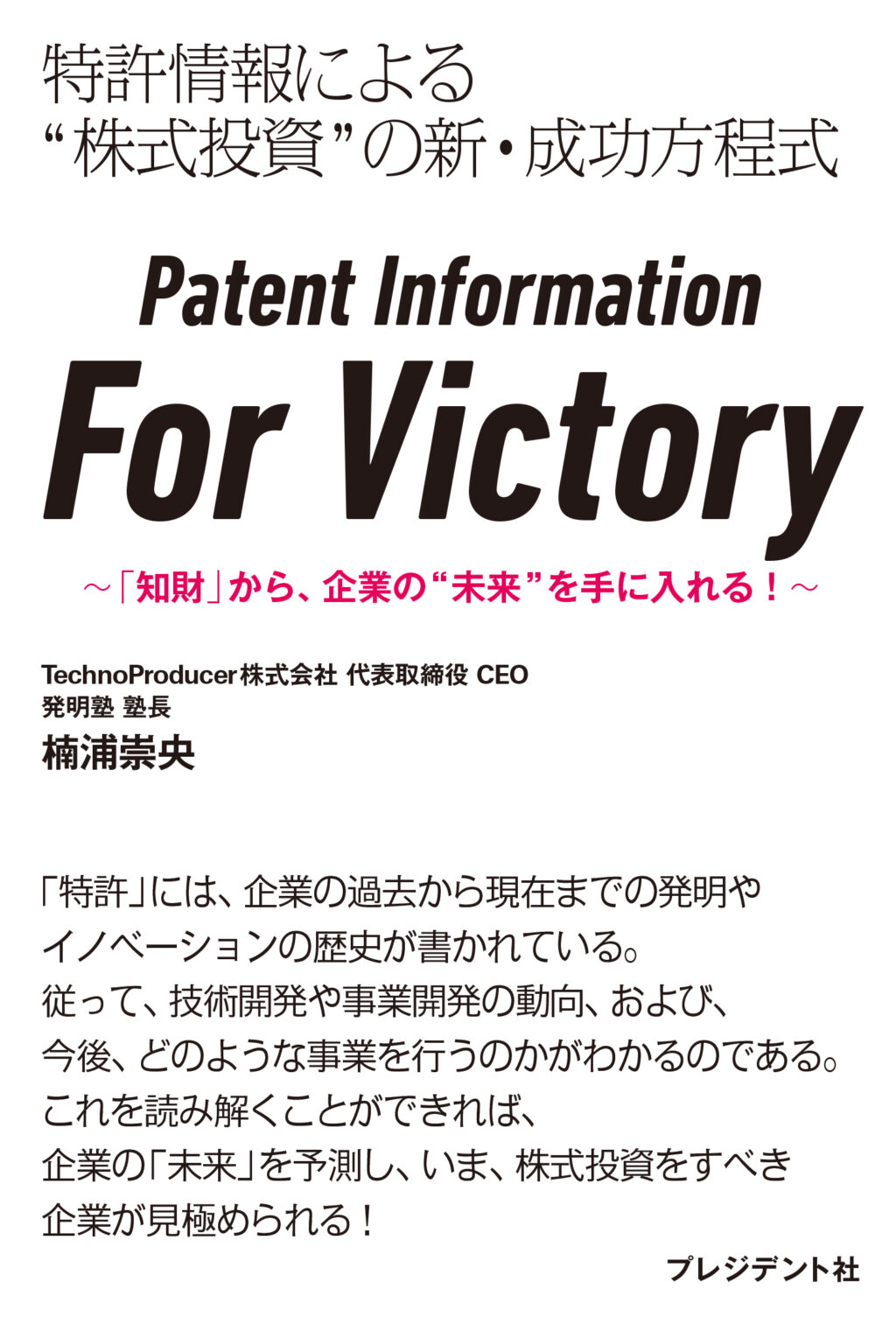
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略